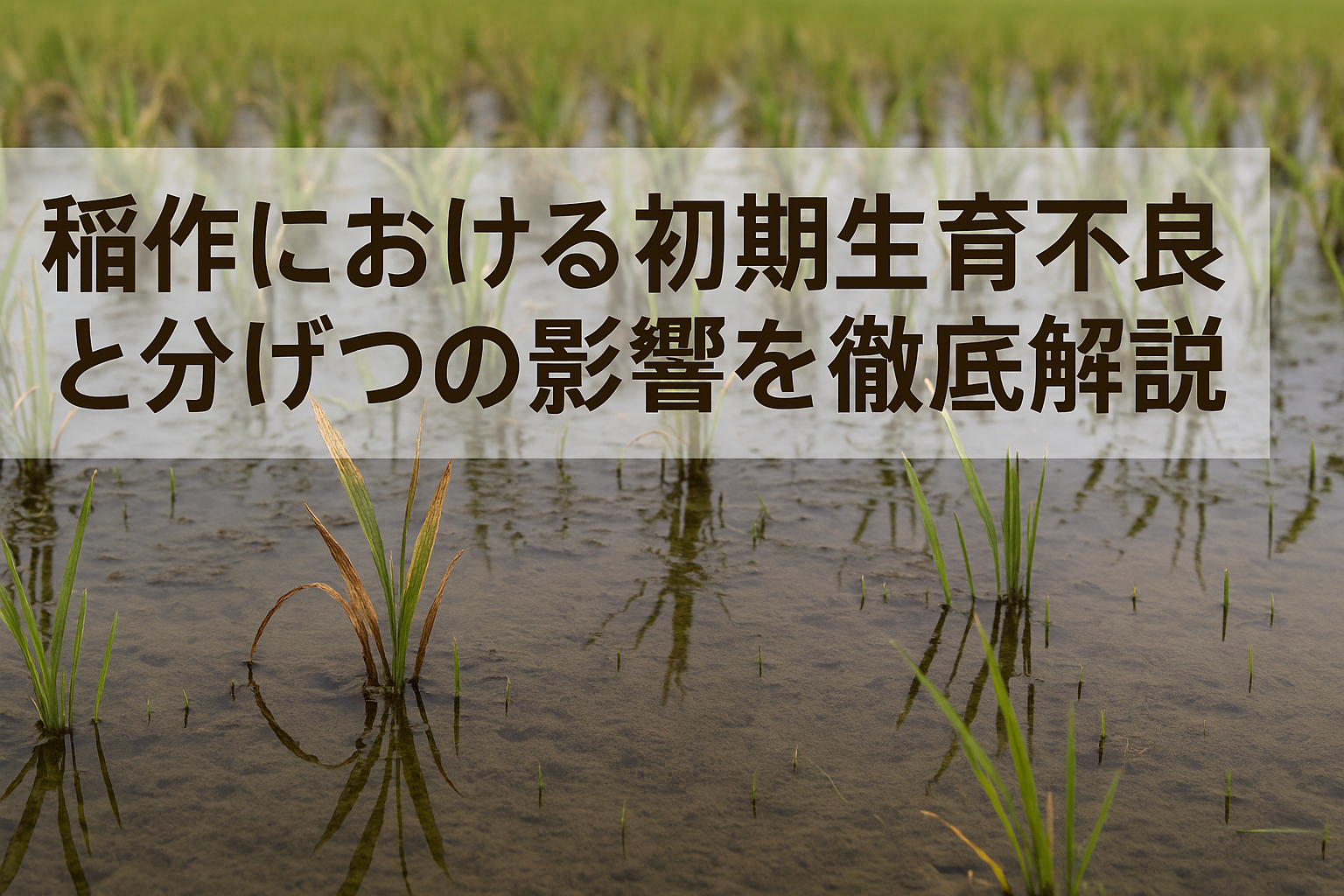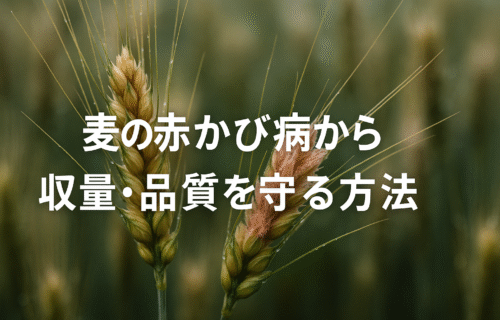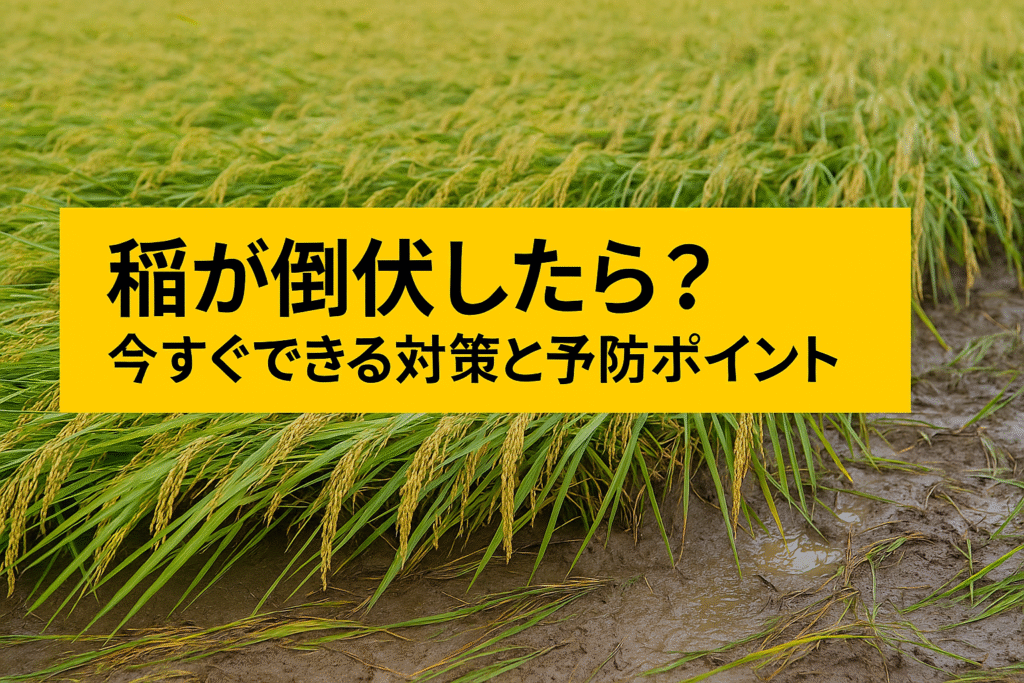
稲作における「倒伏(とうふく)」は、収穫量の減少や品質の低下を招く深刻な問題です。
特に台風や大雨、強風などの自然災害により、育ちきる前に稲が地面に倒れてしまうと、穂が泥に触れたりカビが生えたりして、食味や出荷等級にも悪影響を及ぼします。
さらに、倒れた稲は収穫作業の妨げにもなり、作業効率の低下や機械トラブルにもつながります。
この記事では、倒伏が起きてしまった際の初期対応から、倒伏を未然に防ぐための管理ポイントまで、農家の現場で役立つ具体策をわかりやすく解説していきます。
倒伏とは?その影響とリスク
倒伏とは、稲の茎が途中で折れたり根元から傾いたりして、稲全体が横倒しになる状態を指します。
原因は、強風や豪雨といった外的要因だけでなく、過剰な施肥や過湿、病害虫の被害など、栽培管理のバランスが崩れたことによるケースも少なくありません。
倒伏すると、穂が地面に触れることで病原菌の影響を受けやすくなり、発芽籾や未熟米、カビ米の発生リスクが高まります。
また、コンバインによる収穫作業が難しくなり、収穫時間の延長やロスの増加も避けられません。倒伏を防ぐには、事前の管理と迅速な対応が不可欠です。
倒伏への基本的な対応と初動の重要性

稲が倒伏してしまった場合、最初に重要なのは「迅速な状況把握」と「的確な初動対応」です。倒れたからといってすぐに手を加えるのではなく、まずは倒伏の範囲、程度、原因を見極めることが大切です。
軽度であれば稲を立て直すことで登熟を回復させられる可能性がありますが、重度倒伏では無理に起こそうとせず、別の対策が必要になります。
また、水管理や排水状態もチェックし、倒伏を悪化させないよう注意が必要です。こうした初動の質が、最終的な収量や品質に直結するため、慌てず計画的な対応が求められます。
倒伏発見後はまず被害状況の確認を
圃場で倒伏が確認された場合、まず取り組むべきは「圃場全体の見回り」と「被害の分類」です。倒伏が局所的なものなのか、圃場全体に広がっているのかによって対応方針は異なります。
また、倒れ方にも注目しましょう。茎が途中で折れているのか、根元から浮いているのか、穂が泥に埋まっているのかなど、状態によって回復の可否や対処法が変わってきます。
台風や強風による物理的損傷なのか、それとも栽培管理上の問題(過剰施肥・排水不良など)によるものかを見極めることで、今後の改善策にもつながります。
茎・根元・土壌の観察で原因を特定
倒伏の本当の原因を突き止めるには、稲の茎・根元・土壌の状態を丁寧に観察することが欠かせません。
茎が細くて折れている場合は、窒素の過剰施用や過密な植え付けが原因の可能性があります。根元が浮いていたり、ぐらついていたりする場合は、過湿による根腐れや酸欠が疑われます。
また、土壌が泥濘化していたり、水が引きにくい状態になっている場合は、排水性の悪さが倒伏を助長していると考えられます。これらの情報を整理することで、現場に合った対応や、次作への教訓として活かすことができます。
水管理と排水対策で倒伏を防ぐ

水の管理は、倒伏を防ぐために極めて重要な要素です。特に梅雨や台風などの時期には、圃場が過湿状態になりやすく、稲の根が酸素不足に陥ることで茎が軟弱になり、わずかな風でも倒れてしまう原因となります。
日頃から排水路の整備や、暗渠排水の導入、中干しの実施といった基本対策が効果的です。また、倒伏が起きた後も、水位を急激に変動させず、稲にとってストレスの少ない水環境を維持することが回復のカギとなります。
排水と水位管理の見直しは、単なる倒伏対策にとどまらず、健康な稲を育てる土台づくりでもあります。
過湿状態が招く倒伏リスク
稲の倒伏には、過湿による土壌環境の悪化が大きく関係しています。長雨や台風の後、圃場に水が溜まったままになっていると、根が酸素不足に陥って活力を失い、茎の強度が低下します。
その結果、わずかな風や雨でも茎が倒れてしまいやすくなります。また、酸欠状態が続くと根腐れや病害も誘発され、稲の生育そのものにも悪影響を及ぼします。
見た目では判断しづらい過湿状態こそ、定期的な土壌のチェックと排水状況の確認が欠かせません。圃場がぬかるみやすい地域では、特に注意が必要です。
暗渠排水・溝切りで根本的改善を
水はけの悪さが慢性化している圃場では、一時的な対応だけでは倒伏リスクを根本的に解消できません。そのような場合に有効なのが「暗渠排水」の導入です。
地下に排水パイプを敷設して余分な水を逃がすことで、土壌の通気性が改善され、根張りの良い健全な稲づくりが可能になります。また、圃場の表面に溝を掘る「溝切り」も、比較的手軽な改善手段として有効です。
特に梅雨や台風前のタイミングで事前に溝を整備しておくことで、大雨による冠水や倒伏の発生を予防できます。
倒伏後の水位管理のポイント
すでに倒伏が発生した圃場では、水位の管理が非常に重要です。
水を抜きすぎると土壌が急激に乾燥して根にダメージを与えてしまう可能性がある一方で、水が多すぎると根腐れを悪化させ、稲の回復を妨げます。
適度な湿り気を保ちながら、排水の通り道を確保し、過剰な水分を速やかに逃がす工夫が求められます。また、今後の降雨に備えてあらかじめ水位を低く調整しておくなど、気象状況を踏まえた先手の管理も効果的です。倒伏後の回復を支える環境づくりは、水位の微調整から始まります。
関連記事はこちら
倒れた稲の立て直しと作業の注意点

倒伏してしまった稲でも、状態によっては回復が期待できるケースがあります。特に軽度の倒伏で茎や根に致命的なダメージがなければ、物理的に稲を起こす「立て直し作業」によって登熟を促すことが可能です。
ただし、圃場を踏み荒らしてしまったり、茎を折ってしまうリスクもあるため、丁寧な作業が求められます。併せて水位や施肥も再調整し、稲が自力で立ち上がれる環境を整えてあげましょう。タイミングを見誤ると効果が薄れるため、迅速かつ的確な対応が重要です。
軽度の倒伏は早めの対応がカギ
倒伏直後であれば、根が活きていて茎も柔軟な状態のことが多く、早期に対応すれば立ち直る可能性があります。稲が完全に寝てしまう前に起こしてやることで、再び光合成を活発化させ、登熟の進行を助けることができます。
作業は午前中の気温が低い時間帯に行い、稲を無理に引き起こすのではなく、両側から優しく持ち上げるように行うと、茎や根への負担を軽減できます。起こした後は支柱やヒモで固定することで、風による再倒伏も防げます。
倒伏後に検討すべきケイ酸補給
倒伏した稲を再び健全な状態に戻すためには、ケイ酸の補給が非常に有効です。ケイ酸は稲の細胞壁を強化し、茎を太くしなやかに保つ効果があるため、倒伏予防にも倒伏後の回復にも役立ちます。
特にケイ酸が不足している圃場では、登熟期に追加施用することで稲の立ち上がりをサポートできます。
使用する資材としては、ケイカルや珪酸苦土石灰などが一般的で、10aあたり100~200kgが目安です。倒伏の状況を見ながら、吸収効率の高い資材を選ぶことがポイントです。
さらに、即効性を求める場合には、液体ケイ酸資材「セルマックス」のような吸収効率の高い製品も有効です。
セルマックスはマイクロカプセル化されたケイ酸とカルシウムを含み、葉面や茎部からの浸透性に優れるため、倒伏によって弱った稲の立ち直りをスムーズに促すことが期待できます。圃場の状態や天候に応じて、粒状と液体を使い分けるのが効果的です。
作業時の注意点と費用面のバランス
倒伏の立て直し作業には多くの人手と時間が必要であり、圃場を踏みつけてしまうことで土壌構造を壊したり、健全な株まで傷めてしまうリスクもあります。そのため、作業の必要性と費用対効果のバランスを見極めることが大切です。
倒伏面積が限定的であれば積極的に起こすべきですが、広範囲に及ぶ場合は収穫時期を早める判断も選択肢となります。また、複数人で行う際は役割分担を明確にし、作業の効率と安全性を確保しましょう。
倒伏後の施肥と収穫タイミングを見直す

倒伏が発生した後は、通常どおりの施肥・収穫スケジュールでは対応しきれないことがあります。特に光合成が妨げられた状態では登熟が遅れる可能性があり、適切な栄養補給や収穫のタイミングを再評価する必要があります。
追肥は必要最小限に抑えることが原則で、倒伏の原因が肥料過多にある場合は控える判断も大切です。また、穂が土に接している時間が長引くと品質が低下するため、登熟状況を観察しながら早期収穫の選択も視野に入れましょう。倒伏後は「柔軟な対応」が重要です。
追肥は生育状況を見て慎重に
倒伏により葉が重なった状態では、光の当たり方が偏り、光合成が不十分になります。その結果、登熟に必要な栄養が行き渡りにくくなるため、「追肥した方が良いのでは」と考える人も少なくありません。しかし、倒伏の原因が窒素過多だった場合は、追肥によって症状を悪化させる恐れがあります。
まずは稲の生育ステージや土壌養分を分析し、必要性が高い場合のみ少量施用を検討しましょう。特に登熟期の窒素過多は、いもち病などの病気を引き起こすリスクもあるため注意が必要です。
早期収穫も選択肢の一つ
倒伏によって穂が土に触れてしまうと、カビの発生や穂の発芽など、品質に直結する問題が生じやすくなります。とくに雨が続く時期に長く放置してしまうと、登熟よりも品質劣化のスピードが勝ってしまう可能性があります。
このような場合は、登熟度合いが十分でなくても早めに刈り取る判断が必要になることがあります。もちろん、早期収穫には収量や食味への影響が伴うため、気象予報や乾燥施設の空き状況、JAのアドバイスなどを踏まえた上で、総合的に判断することが重要です。
倒伏を防ぐ日頃の管理ポイント

倒伏は天候だけが原因ではありません。日頃の栽培管理こそが、倒伏を防ぐための最大の鍵です。適切な品種選定、肥培管理、水管理、植え付け密度の調整など、日々の積み重ねが稲の体づくりに直結します。
稲がしっかりと根を張り、太く丈夫な茎に育つように、栄養バランスと生育環境を見極めながら栽培を進めることが重要です。倒伏が発生してから対処するよりも、発生を未然に防ぐ「予防的アプローチ」を常に意識しましょう。
耐倒伏性品種を選ぶ
倒伏リスクを減らすうえで有効なのが、耐倒伏性に優れた品種の導入です。最近の品種改良では、茎が太く短めで風雨に強い稲が数多く登場しています。地域の気象条件や土壌特性に合った品種を選ぶことで、日頃の管理負担も軽減できます。
各地のJAや試験場では、品種特性・収量・耐病性などの情報が整備されているため、事前に相談するのもおすすめです。品種選びの段階から「倒伏しにくい稲づくり」は始まっています。
肥培管理の基本を押さえる
肥料のやり過ぎは倒伏の主な原因のひとつです。特に窒素が過剰になると、稲は徒長し、茎が細く軟弱になります。その結果、強風や豪雨で簡単に倒れてしまいます。
施肥を行う前には土壌分析を行い、養分バランスを把握することが基本です。窒素・リン酸・カリのバランスを意識し、無理なく分げつが進むように調整しましょう。過剰な肥料は品質の低下や病害の誘発にもつながるため、計画的かつ段階的な施肥設計が求められます。
ケイ酸で茎を補強する
稲の茎を強くし、倒伏を防ぐためには「ケイ酸」の補給も非常に効果的です。ケイ酸は植物の細胞壁を強化し、茎を太く硬く保つ役割があります。ケイ酸が不足すると、稲の茎が軟弱化し、風や雨の影響を受けやすくなります。
倒伏しやすい圃場では、ケイカルや珪酸苦土石灰などのケイ酸質肥料を、10aあたり100〜200kg程度施用するのが一般的です。とくに秋〜翌春にすき込むことで、次作の耐倒伏性向上につながります。
先ほども伝えましたが、効性を求める場合には、液体ケイ酸資材「セルマックス」のような吸収効率の高い製品も有効です。
関連記事はこちら
段階的な施肥で生育をコントロール
稲の生育ステージごとに適した施肥を行うことも、倒伏防止には欠かせません。
分げつ期には窒素を適度に与えて株数を確保し、茎数を増やすことが大切ですが、穂ばらみ期や登熟期に過剰な窒素を与えてしまうと、かえって茎が軟弱になって倒れやすくなります。
施肥は「初期・中期・後期」の三段階で設計し、それぞれの時期に必要な栄養素をバランスよく供給するようにしましょう。こうした段階的な管理が、稲の安定した生育と収穫を支えます。
関連記事はこちら
株間と病害虫対策も忘れずに

倒伏を防ぐためには、施肥や水管理だけでなく、株間の設計や病害虫の防除といった基本的な管理も見逃せません。過度な密植は風通しを悪くし、稲が細く軟弱に育ってしまう原因になります。
また、湿度が高まることで病害虫の発生リスクも上昇し、茎を侵食されると倒伏に直結します。こうした環境をつくらないためにも、適正な植え付け密度と、定期的な巡回による早期の異常発見が重要です。小さな管理の積み重ねが、倒伏しにくい圃場環境を支えます。
密植を避けて風通しを確保
密植は稲同士が競合し、十分な日照や栄養を得られない原因になります。特に茎の成長が妨げられやすくなり、結果として細く柔らかい茎になりやすいのです。さらに風通しの悪さから湿度が高まり、病害虫の温床にもなりかねません。
品種や地域によって最適な植え付け密度は異なりますが、目安としては条間30cm〜33cm程度、株間は13cm〜15cm前後が一般的です。健全な株づくりのためにも、密度設計を見直しましょう。
病害虫の早期発見と防除を徹底
ウンカ類やいもち病などの病害虫は、稲の茎や葉を侵し、結果として倒伏を誘発します。高温多湿な環境では、特に病害虫の発生が活発になりやすく、早期対応が重要になります。
防除の基本は「早期発見・早期対応」です。定期的に圃場を巡回し、わずかな異変も見逃さないようにしましょう。薬剤散布を行う場合は、稲の生育ステージと天候を見極め、適正なタイミングと量で施すことが大切です。健全な茎を保つことが、倒伏防止にも直結します。
水管理と刈り取り時期の調整

倒伏を防ぐためには、水の管理と刈り取りのタイミングにも気を配る必要があります。過剰な水分は根の酸欠や軟弱茎の形成を招き、倒伏の原因となります。
一方、適切な中干しを行うことで、根が深く張り、株元がしっかりして倒れにくくなります。また、収穫時期が台風や長雨と重なることが予想される場合には、登熟具合を見ながら早めに刈り取る判断も重要です。
これらの水と収穫のタイミングをうまく調整することで、倒伏リスクを大幅に軽減できます。
中干しの活用で根張りを促進
分げつ後半から穂ばらみ期にかけて行う中干しは、倒伏防止において極めて重要な工程です。田んぼに一時的に水を抜いて乾燥させることで、土壌中に酸素が供給され、稲の根がより深く張るようになります。
これにより、稲株が倒れにくくなり、養分吸収力も高まります。中干しの期間は7〜10日程度が目安で、土がひび割れるくらいまで乾かすのが理想です。ただし、乾きすぎは逆効果となるため、適度なタイミングで再灌水するよう心がけましょう。
台風前の早期刈り取り判断
登熟期を迎えた稲は、穂が重くなることでわずかな風でも倒れやすくなります。特に台風の接近が予想される場合は、倒伏による収穫ロスや品質低下を防ぐために、早期収穫の判断が求められます。
収穫の目安としては、籾の乳白期を過ぎて黄化が進んだ段階が理想です。収量や食味への影響を最小限に抑えるためにも、天候予報を注視しながら、施設の稼働状況や乾燥のタイミングなども含めて総合的に判断しましょう。
まとめ:倒伏を防ぐには“総合的な管理”がカギ
稲の倒伏は、一度起きてしまうと収穫量や品質に大きなダメージを与える深刻な問題です。しかし、原因を正しく理解し、適切な管理を日頃から行うことで、倒伏のリスクは大幅に低減できます。
耐倒伏性品種の選定、バランスの取れた肥培管理、ケイ酸の補給、水管理の工夫、そして病害虫の早期防除——こうした一つひとつの対策を組み合わせて実践することが、倒伏に強い稲を育てる鍵です。
自然条件に左右されやすい稲作だからこそ、日々の小さな工夫と積み重ねが大きな差を生み出します。収量と品質を守るためにも、倒伏対策は“予防”から取り組みましょう。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。

あなたの圃場、肥料足りてますか?
LINEで無料!水稲の肥料設計を診断します!
地域や土壌に合わない肥料設計は、収量や品質に大きな影響を及ぼします。
LINE登録していただき、質門に答えるだけであなたの栽培条件に合わせた
水稲向けのおすすめ肥料設計を無料でご提案!
- 土壌の傾向や天候も考慮したアドバイス
- 追肥や元肥のタイミングもわかる!
- 今使っている肥料で足りるか診断可能