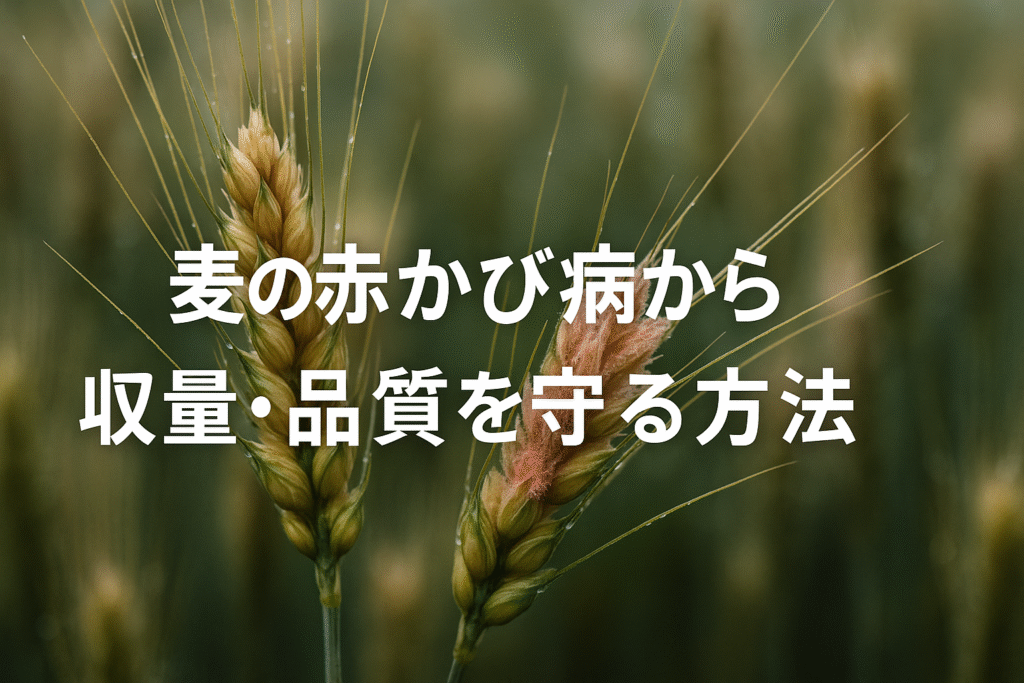
麦作りで最も注意したい病気の一つが「赤かび病」です。この病気は小麦や大麦などに大きな被害をもたらし、収穫量が減るだけでなく、人や家畜の体に害のある毒素を作り出すことで知られています。
赤かび病は梅雨の時期の暑くて湿った天気で特に発生しやすく、一度広がると防ぐのが難しくなります。そのため、事前の対策と正しいタイミングでの防除がとても大切です。最近の気候の変化で発生する危険が高まっているため、正しい知識と対策方法を覚えることが必要です。
この記事では、赤かび病の基本的な知識から具体的な防ぎ方、予防方法まで、農家の皆さんが実際に使える内容をわかりやすく説明します。正しい対策で、健康な麦作りと安定した収入を目指しましょう。
麦の赤かび病とは?基本的な病気の特徴
赤かび病は、フザリウムというカビの仲間が起こす麦の重要な病気です。この病気の一番の問題は、病気になった麦粒に「マイコトキシン」という毒素を作ることです。マイコトキシンは人や家畜が食べると体調不良を起こす可能性があるため、食べ物の安全性の面でもとても重要です。
病気の菌は主に麦の花が咲く時期から実が入る時期にかけて麦の穂に入り込み、穂全体を赤茶色に変色させます。病気になった穂は「赤かび穂」と呼ばれ、遠くから見ても健康な穂との違いがはっきりとわかります。病気の菌は土の中や枯れた植物で冬を越し、次の年の病気の元になるため、継続的な対策が必要です。
この病気は世界中の麦作り地域で問題となっており、日本では特に梅雨時期の高温多湿な天気が発生を手助けします。一度病気が始まると短期間で急速に広がるため、早く見つけて素早く対応することが被害を減らすポイントです。
赤かび病の原因となる菌の種類と特徴
赤かび病を起こす菌は、主に2つの種類があります。一つ目は「フザリウム・グラミネアラム」、二つ目は「フザリウム・アベナセウム」です。これらの菌は形や性質が少し違いますが、どちらも麦に深刻な被害をもたらします。
フザリウム・グラミネアラムは最も一般的な病気の菌で、「デオキシニバレノール(DON)」という毒素を主に作ります。この菌は比較的暖かい温度を好み、25~28℃の条件で最も活発に活動します。一方、フザリウム・アベナセウムは少し涼しくても活動でき、「ニバレノール」という別の毒素を作る特徴があります。
これらの病気の菌は、麦の花が咲く時期に風や雨によって穂に運ばれて感染します。カビの糸は麦の花から入り込み、穂の軸や小さな穂、さらには麦粒の中まで進んでいきます。感染した部分では菌が急速に増え、赤茶色の胞子(カビの種のようなもの)を大量に作って、さらに病気を広げる原因となります。
麦の赤かび病の症状と見分け方
穂の症状
赤かび病の最も特徴的な症状は穂に現れます。病気の初期では、穂の一部に水がしみたような暗い緑色の斑点が現れ、だんだん赤茶色からピンク色に変わっていきます。病気が進むと、感染した部分にはオレンジ色から赤色の粉のような物質が作られ、これが「赤かび」という名前の由来になっています。
ひどい感染では穂全体が赤茶色に変色し、正常な緑色の部分がほとんど見えなくなります。このような穂は「赤かび穂」と呼ばれ、収穫の時まで残るので簡単に見分けることができます。また、病気になった穂は軽くなり、風で揺れやすくなるという特徴もあります。
湿度が高い条件では、感染した部分に白色からピンク色の綿毛のようなカビが見えることもあります。これは病気の菌の糸と胞子が集まった状態で、感染の確実な証拠となります。
茎や葉の症状
赤かび病は主に穂の病気ですが、ひどい場合には茎や葉にも症状が現れることがあります。茎では節の部分に暗い茶色の病斑ができ、病気が進むと茎が柔らかくなって倒れやすくなります。
葉では茎を包む葉の基部に水がしみたような病斑が現れ、だんだん茶色に変わります。しかし、葉の平たい部分への感染はまれで、主に茎を包む部分や茎に限られるのが一般的です。
これらの症状は他の病気(うどんこ病、さび病など)と間違えやすいため、穂の症状と合わせて総合的に判断することが大切です。
粒への影響
赤かび病にかかった麦粒は、見た目と中身の品質の両方に深刻な影響を受けます。感染した粒は正常な粒と比べて小さく、しわが寄ったような見た目になります。色も健康な麦粒の黄金色ではなく、白色からピンク色、時には黒色に変わります。
中では、病気の菌によってでんぷんやタンパク質が分解されるため、粒の重さが大幅に減ります。また、最も重要な問題として、感染した粒には高い濃度の毒素が蓄積されます。これらの有害物質は加熱処理でも完全に取り除くことができないため、食品の安全性で大きな問題となります。
感染した粒の割合が高くなると、収穫物全体の品質が著しく悪くなり、市場での価値が大幅に下がってしまいます。ひどい場合には食品として使うことが困難になり、飼料としても制限される可能性があります。
赤かび病が発生しやすい条件と時期
天気の条件
赤かび病の発生には、気温と湿度が密接に関係しています。最も発生しやすい条件は、気温が20~28℃で、湿度が85%以上の状態が48時間以上続く場合です。このような条件は日本では梅雨時期によく見られるため、この時期の感染リスクが特に高くなります。
雨は病気の菌の胞子を穂に運ぶ重要な要因です。特に花が咲く時期前後の雨は感染リスクを大幅に高めるため、天気予報を注意深く見ることが必要です。また、朝露や霧も感染に必要な湿度を与えるため、これらの天気が続く場合は注意が必要です。
風は病気の菌の胞子を広い範囲に散らばらせる役割をします。強い風により隣の畑からの感染が起こることもあるため、地域全体で協力した防除対策が重要となります。
栽培環境
畑の場所の条件も赤かび病の発生に大きく影響します。水田から畑に変えた土地や水はけの悪い畑では、土の湿度が高くなりやすく、病気の菌の活動が活発になります。また、風通しの悪い畑では湿度が高く保たれるため、感染リスクが高まります。
栽培の密度も重要な要因です。種を蒔きすぎて株の間が狭くなると、風通しが悪くなり湿度が高くなりがちです。また、窒素肥料をやりすぎると茎や葉が茂りすぎて、畑の中の湿度上昇と病気の菌の増殖を助けます。
前の作物の残りかすも感染源になる可能性があります。特に麦類やトウモロコシの残りかすには病気の菌が潜んでいることが多いため、適切な処理が必要です。
発生時期
小麦では5月中旬から6月上旬、大麦では4月下旬から5月中旬がリスクの高い時期となります。この時期は麦の花が開き、病気の菌が入りやすい状態になっているためです。
感染してから症状が現れるまでの期間は天気の条件により違いますが、一般的に7~14日程度です。梅雨入り後の高温多湿な条件では、感染から数日で症状が現れることもあります。
収穫期直前の雨も感染リスクを高めます。この時期の感染は症状が軽くても、毒素の蓄積が進むため品質への影響が深刻になる可能性があります。
麦の赤かび病による被害と経済的な影響
収穫量への影響
赤かび病による収穫量の損失は、感染の程度により大きく違います。軽い感染でも5~10%の減収となり、ひどい感染では50%以上の収穫量損失も報告されています。感染により麦粒の成長が邪魔され、1000粒の重量が大幅に減ることが主な要因です。
感染した穂では正常な実の入りが行われないため、粒数の減少も起こります。また、感染により穂全体が枯れる場合もあり、このような穂からは収穫できる麦粒がほとんど得られません。
早い時期の感染ほど収穫量への影響が大きくなるため、花が咲く時期前後の防除対策が収穫量確保において極めて重要となります。
品質への影響
赤かび病は収穫量だけでなく、麦の品質にも深刻な影響を与えます。感染した粒は見た目の品質が著しく悪くなり、正常な粒との選別が困難になります。小麦では粉にする歩留まりが下がり、パンや麺類の品質にも悪い影響を与えます。
大麦では醸造用として使うことが困難になり、発芽率の低下により麦芽としての価値が失われます。また、感染により麦粒のタンパク質含量やでんぷんの組成が変わり、加工への適性が大幅に下がります。
これらの品質の悪化により、等級が下がったり用途が制限されたりして、販売価格の大幅な下落につながります。
毒素汚染のリスク
赤かび病の最も深刻な問題は、毒素による汚染です。「デオキシニバレノール(DON)」や「ニバレノール」などの毒素は、人や家畜に吐き気、下痢、免疫機能の低下などの健康被害を起こす可能性があります。
日本では食品衛生法により、小麦中のDON濃度に基準値(1.1ppm)が決められており、これを超えた麦は食品として使うことが禁止されます。このため、軽い感染でも商品価値が完全に失われる可能性があります。
毒素は加熱や洗浄では取り除くことができないため、予防対策による感染防止が唯一の対策となります。このことが赤かび病対策の重要性を高める最大の理由です。
赤かび病の予防対策
栽培管理による予防
適切な栽培管理は赤かび病の予防において最も基本的で重要な対策です。まず、適正な種まきの密度を保つことで、畑の中の風通しを良好に保ち、湿度の上昇を抑えることができます。一般的に、小麦では10a当たり5~6kg、大麦では8~10kgの種まき量が推奨されます。
肥料の管理では、窒素肥料をやりすぎないことが重要です。窒素が多すぎると茎や葉が茂りすぎて、畑の中の湿度を高めて病気の菌の活動を活発にさせます。土壌診断に基づいた適正な施肥を心がけ、特に穂肥の時期と量には注意が必要です。
水はけ対策も予防の重要な要素です。水路や暗渠の設置により畑の水はけを改善し、土の湿度の過度な上昇を防ぎます。また、畝を立てた栽培により根の周りの水はけを良くすることも効果的です。
品種選択
品種選択は赤かび病対策において最も確実で経済的な方法の一つです。近年、品種改良技術の進歩により、赤かび病に強い品種が開発されています。これらの病気に強い品種は、同じ条件でも感染リスクが大幅に軽減されます。
小麦では「きぬあかり」「ゆめちから」「きたほなみ」などが比較的病気に強いとされています。大麦では「はるしずく」「サチホゴールデン」などが推奨されます。ただし、完全に病気にかからないわけではないため、他の対策と組み合わせることが重要です。
品種を選ぶ際は、地域の気候条件や栽培方法に適したものを選ぶことが大切です。また、収穫量や品質の特性とのバランスも考えて、総合的に判断することが必要です。
畑の環境改善
畑の周りの環境を整えることも予防対策として重要です。麦類やトウモロコシなどの残りかすは病気の菌が冬を越す場所となるため、収穫後は速やかに取り除くか適切に処理します。深く耕すことで残りかすを土の中に埋めることで、菌の密度を減らすことができます。
輪作による予防効果も期待できます。イネ科以外の作物(大豆、野菜類など)との輪作により、病気の菌の密度を減らすことができます。最低でも2年、できれば3年以上の輪作間隔を設けることが推奨されます。
畑の周りの雑草管理も重要です。麦類に近い雑草(スズメノテッポウ、ネズミムギなど)は病気の菌の中継地点となる可能性があるため、適切に除草することが必要です。
赤かび病の防除方法
薬剤散布による防除
薬剤による防除は赤かび病対策において最も確実で即効性のある方法です。現在、赤かび病に使える主要な殺菌剤には、トリアゾール系(テブコナゾール、プロピコナゾールなど)、ストロビルリン系(アゾキシストロビンなど)、多作用点阻害剤(チウラムなど)があります。
薬剤を選ぶ際は、効き方の違う薬剤の組み合わせや、成分の違う薬剤を順番に使うことで、薬剤への抵抗性ができることを防ぐことが重要です。また、地域の病気の菌の薬剤への感受性情報を参考に、最も効果的な薬剤を選びます。
散布方法では、均一で十分な薬液の付着を確保することが重要です。散布量は一般的に10a当たり100~150Lとし、穂全体に薬液が十分付着するよう丁寧に散布します。風の強い日や雨の日の散布は避け、適切な天気の条件で実施することが効果向上のポイントです。
微生物を使った防除
微生物を使った防除は、役に立つ微生物を利用して病気の菌の活動を抑える環境に優しい防除方法です。近年、赤かび病に対してもバチルス属の細菌や対抗する菌を利用した生物農薬の開発が進んでいます。
これらの微生物は、病気の菌との栄養の取り合いや抗菌物質の産生により、赤かび病の発生を抑えます。また、植物の免疫システムを活性化させる効果も報告されており、総合的な病気の抑制に貢献します。
微生物による防除の利点は、薬剤抵抗性の心配がなく、環境への負荷が少ないことです。ただし、効果が現れるまでに時間がかかる場合があり、天気の条件に影響されやすいという制約もあります。薬剤による防除と組み合わせた総合的な病気管理での利用が推奨されます。
物理的な防除
物理的な防除には、畑の環境改善による病気の菌の活動抑制が含まれます。適切な栽培密度を維持することで風通しを改善し、畑の中の湿度を下げることが基本となります。
また、マルチ栽培による土からの水分蒸発抑制や、防風ネットの設置による風による胞子の飛散防止なども物理的防除の一つです。これらの方法は直接菌を殺す効果はありませんが、病気の菌の感染に適した環境条件を避けることで予防効果を発揮します。
さらに、収穫後の適切な乾燥処理により、毒素の産生を抑えることも重要な物理的対策です。収穫した麦の水分含量を14%以下まで速やかに乾燥させることで、貯蔵中の品質悪化を防ぐことができます。
散布時期とタイミングの重要性
赤かび病防除における散布タイミングは、防除効果を左右する最も重要な要素です。最適な散布時期は麦の花が咲く時期で、具体的には花が咲き始め(20~30%開花)から花盛り(70~80%開花)の期間が推奨されます。この時期の散布により、病気の菌の初期感染を効果的に防ぐことができます。
天気の条件も散布タイミングの決定に重要な役割をします。花が咲く時期前後に雨が予想される場合は、雨の前に予防散布を実施することが効果的です。また、散布後24時間以内の雨は薬の効果を大幅に下げるため、天気予報を十分確認してから散布を行います。
追加散布の判断基準として、初回散布後10~14日経過時点での天気の条件と病気の発生状況を評価します。梅雨が長引き高湿度な条件が続く場合や、周りの畑で病気が確認された場合は、追加散布を検討します。ただし、薬剤の使用回数制限や収穫前の日数制限を守ることが法的に求められます。
赤かび病発生後の対応策
赤かび病の発生が確認された場合、被害拡大を防ぐための素早い対応が必要です。まず、病気になった株や穂を早期に見つけ、できる限り取り除きます。感染した穂は伝染源となるため、畑の外に持ち出して適切に処分することが重要です。
治療効果のある殺菌剤の散布も有効ですが、病気になった後の散布は予防散布ほど高い効果は期待できません。それでも、被害拡大の抑制と毒素産生の軽減効果があるため、適切な薬剤を選んで散布します。
収穫時期の調整も重要な対応策です。赤かび病にかかった麦は、畑での乾燥期間中に毒素の産生が進むため、適期収穫を心がけます。ただし、水分含量が高い状態での収穫は乾燥コストの増加を招くため、天気の条件を見ながら最適なタイミングを判断します。
収穫物の適切な分別も必要です。明らかに感染した穂や粒は取り除き、健康な部分との混合を避けます。また、収穫後は速やかに乾燥処理を行い、毒素産生の進行を止めることが重要です。
今後の研究動向と新しい防除技術
赤かび病防除技術の研究開発は現在も活発に進められており、いくつかの有望な新技術が実用化に向けて開発されています。遺伝子マーカーを利用した病気に強い品種の効率的な品種改良技術により、より強い抵抗性を持つ品種の開発が進んでいます。
新しい殺菌剤の開発では、今ある薬剤とは違う効き方を持つ化合物の探索が進んでいます。特に、毒素産生を直接阻害する薬剤の開発は、食品安全の観点から注目されています。
精密農業技術を活用した防除システムの開発も進んでいます。ドローンを利用した畑の監視や、AIを活用した病気の発生予測システムにより、より効率的で確実な防除が可能になると期待されています。
また、生物農薬や天然物由来の防除資材の開発も活発化しており、環境に優しい持続可能な防除体系の構築が進められています。これらの新技術と従来技術を組み合わせた総合的な管理により、より効果的で経済的な赤かび病対策が実現されると期待されます。
まとめ:効果的な赤かび病対策のポイント
麦の赤かび病対策を成功させるためには、予防、早期発見、適期防除、そして収穫後管理の各段階で適切な対策を行うことが不可欠です。最も重要なのは予防対策で、病気に強い品種の選択、適正な栽培管理、畑の環境改善により、感染リスクを大幅に軽減できます。
薬剤による防除では、花が咲く時期の適期散布が防除効果を最大化するポイントとなります。天気情報を活用した散布タイミングの決定と、地域の病気の菌に効果的な薬剤の選択により、確実な防除効果が期待できます。
病気になった後の対応では、被害拡大防止と品質保持のための迅速な対応が重要です。感染部位の除去、治療的散布、適期収穫により、被害を最小限に抑えることができます。
今後は新技術の活用により、より効率的で持続可能な防除体系の構築が期待されます。農家の皆さんには、基本的な防除技術を確実に実践するとともに、新しい情報や技術の習得に努めていただき、安全で高品質な麦の生産を継続していただきたいと思います。適切な赤かび病対策により、安定した収穫量と品質を確保し、持続可能な麦作り経営を実現しましょう。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。
\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/
LINE登録で「肥料パンフレット」&
「お悩み解決シート」進呈中!
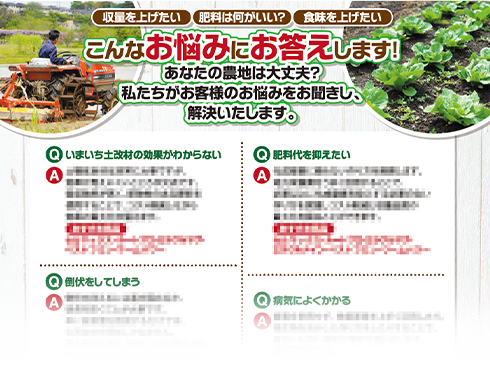
「どの肥料を使えばいいかわからない」
「生育がイマイチだけど、原因が見えない」
そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!
プレゼント内容
- 肥料の選び方がわかるパンフレット
- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」
LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!










