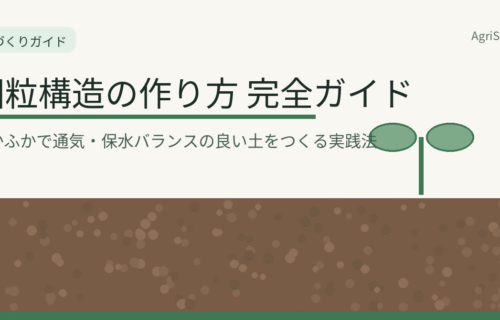堆肥は農業やガーデニングに欠かせない土づくりの要です。作物に必要な栄養を補うだけでなく、土壌環境を改善し、持続可能な農業を支える役割を果たします。
近年は環境保全の観点からも注目され、廃棄物を再資源化する循環型の仕組みとして重要視されています。特に「植物性堆肥」は落ち葉やわら、もみ殻など、身近な材料で簡単に作ることができるため、家庭菜園から大規模農家まで幅広く活用されています。
一方で「動物性堆肥」は家畜のふん尿などを利用し、より高い肥料効果が見込める反面、臭いや取り扱い方法にも注意が必要です。
本記事では、堆肥の基礎知識や肥料との違い、種類や特徴、具体的な作り方や使い方までを総合的に解説します。最後まで読んでいただくことで、堆肥のメリットを最大限に活かせるようになり、あなたの農業・園芸がより豊かで持続可能なものになるでしょう。
堆肥とは?

堆肥は、動植物由来の有機物を微生物の働きによって分解・発酵させた資材のことです。栄養分を補給する「肥料的な役割」に加え、土壌の保水性や通気性を高める「土壌改良」の効果も期待できます。
単に作物を育てるための肥料としてだけでなく、土壌生態系のバランスを整え、持続可能な生産環境を築く基盤となる点が特徴です。また、廃棄物を再利用する形で作られるため、環境負荷を軽減しながら循環型社会の実現にも寄与します。
家庭菜園でも気軽に始められる反面、微生物活動を促すための水分管理や温度管理など、正しい知識と手間が必要です。しかし、適切に作り、上手に活用することで、化学肥料の使用を減らし、土壌の活力を長期にわたって維持する大きなメリットを得られます。
堆肥について
堆肥は生ごみや落ち葉、家畜の排せつ物など、さまざまな有機物を発酵させることで生み出されます。微生物が活発に活動しやすい温度帯(約50~70℃)が保たれることで、雑菌や害虫の卵なども死滅し、安全性の高い有機質資材となるのが特長です。
微生物の働きが進むと独特の発酵臭が軽減され、黒褐色のふかふかした素材になります。堆肥は単に肥料分として窒素・リン酸・カリウムなどを補うだけでなく、土の団粒構造を改善し、空気や水が通りやすい土壌づくりに大きく貢献します。
こうした機能のおかげで、作物の根がのびのび育ち、健康的かつ高品質な収穫が期待できます。
肥料と堆肥の違い
肥料は主に作物の生育を促進するための栄養源を供給する目的で使用され、化学合成によるものや有機由来のものなど、種類は多岐にわたります。
一方、堆肥は栄養補給に加え、土壌そのものの構造を改善する効果が大きい点が大きな違いです。
化学肥料は即効性が高い反面、長期的には土壌のバランスを崩す恐れもありますが、堆肥はゆっくりと有機物を分解しながら養分を供給するため、土壌の生態系を大切にしつつ、持続的な土づくりが行えます。
加えて、堆肥づくりは廃棄物の削減にもつながり、環境面から見てもメリットの大きい取り組みです。
堆肥の種類と材料

堆肥には大きく分けて「植物性堆肥」と「動物性堆肥」があります。
植物性堆肥は、落ち葉・わら・もみ殻などの植物由来の有機物を主成分とし、比較的扱いやすく、初心者でも始めやすい点が特徴です。
一方、動物性堆肥は家畜の排せつ物や原料となり、窒素やリン酸などの成分が豊富かつ、土壌の物理性の改善などで使用されることも多いです。
ただし、動物性由来の資材は独特のにおいや衛生面での配慮が必要となるため、保管場所や施用時期にも注意が必要です。いずれも上手に取り入れれば、土壌に多様な有機物を供給し、豊かな生態系を育む土づくりが実現します。
ここからは、具体的な材料に焦点を当て、それぞれの特徴や作り方を詳しく見ていきましょう。
植物性堆肥
植物性堆肥は、家庭菜園から大規模農業まで幅広い場面で活用される人気の高い資材です。植物残渣(ざんさ:作物の残りカス)、草木の切れ端、米ぬかなど、身近に手に入りやすい素材を使うため、導入コストが低いのがメリットです。
微生物による分解が穏やかで、施用後の土壌に負担が少ないことも魅力。発酵過程で極端な高温に達しにくく、作り方も比較的シンプルで初心者向きです。
一方、即効性がやや低いため、作物の栄養補給に速効性を求める場合は、別途追肥などの組合せが必要になります。
落ち葉堆肥(腐葉土)
落ち葉堆肥は、落ち葉を積み重ねて発酵させることでできる腐葉土が代表的です。庭先や公園で集めた落ち葉を活用できるため、資源を有効に再利用できる点がポイント。
適度に水分を保ちつつ、空気を含むよう混ぜ込むことで発酵が促進され、ふかふかとした腐葉土が完成します。土壌をやわらかくする効果が高く、家庭菜園や花壇などあらゆる場所で使いやすい万能な堆肥です。
落ち葉にカビが生える過程は自然の分解作用でもあるため、過度に敬遠せず、微生物が働きやすいよう温度や湿度を調整しましょう。
わら堆肥(稲わら)
稲わらをベースにした堆肥は、米作農家や稲作が盛んな地域でよく利用されます。わらは炭素源が豊富なため、窒素源となる他の有機物(例:生ごみや鶏ふん)と組み合わせると、微生物が活発に分解を進めやすいバランスになります。
わら自体はゆっくりと分解が進み、土壌中の微生物を増やしながら徐々に有機物を供給するため、長期的に土壌を改善する効果が期待できます。また、わらが土壌表面を覆う「マルチング」の役割を果たすことで、乾燥や雑草の抑制にも役立ちます。
バーク堆肥
バーク堆肥は、主に樹皮(バーク)を発酵させて作る堆肥です。林業や製材所などで大量に発生する樹皮を再資源化できるため、森林資源の有効活用にもつながります。
バークは繊維が多く通気性に優れており、完成した堆肥は土の排水性や保水性を高める効果が大きいです。特に果樹園や花木を育てる際に好んで使われ、土壌の通気性を確保しながら徐々に有機物を補うことができます。
ただし、発酵期間が長めで、途中で水分調整や切り返し作業が必要となる場合があるため、じっくりと管理することが大切です。
もみ殻堆肥
もみ殻堆肥は、米の精米過程で出る「もみ殻」を活用した堆肥です。もみ殻は軽く、通気性が良いため、堆肥化することで土壌をふかふかにしてくれるのが特徴です。
発酵の過程では高温になりやすく、雑草の種や病原菌を抑制する効果も期待できます。また、もみ殻にはケイ酸が含まれ、作物の茎や葉を丈夫にするメリットがあります。
もみ殻単独では窒素分が不足しがちなので、米ぬかや家畜ふんなど窒素源を適度に加えると、バランスの良い堆肥に仕上がります。
動物性堆肥
動物性堆肥は、家畜や家禽などの排せつ物を主体とするため、窒素やリン、カリウムなどの栄養素が豊富に含まれています。
即効性の高い栄養補給が期待できる一方、においや病原菌リスクを抑えるため、しっかりと発酵・熟成させることが必須です。発酵が進んでいない状態で施用すると、作物の根を傷める原因となったり、ハエなどの害虫を呼び寄せる可能性もあります。
動物性堆肥は作物への肥培管理を強化したいときに有効ですが、土壌中の微生物バランスを崩さないように注意深く活用しましょう。
牛ふん堆肥
牛ふん堆肥は、牛のふんにわらや敷料を混ぜ、発酵させることで作られます。牛の腸内細菌はセルロースを分解する力が強く、未消化の繊維分を多く含むことから、土壌に有機物をたっぷりと供給できるのが特徴です。
また、窒素分が適度に含まれており、野菜や果樹など幅広い作物に使われます。完熟させる過程では高温が出やすく、病原菌や雑草の種を抑える効果も期待できます。施用量を間違えると塩分過多になる場合があるため、土壌診断や適切な施用量の把握が大切です。
豚ぷん堆肥
豚ぷん堆肥は、牛ふんに比べてやや窒素やリン酸の含有量が高いといわれており、野菜栽培などで速やかな栄養補給を狙う場合に活躍します。
ただし、豚の飼料によっては残留抗生物質や塩分量の影響が懸念されるため、信頼できる生産者・業者が発酵管理を適切に行ったものを選ぶことが重要です。
豚ぷんは水分量も多いので、発酵過程でしっかり切り返すことで、においを抑えつつ熟成度を高められます。家庭菜園でも使いやすい資材ですが、臭気対策や土壌とのバランスを考慮しながら施用しましょう。
鶏ふん堆肥
鶏ふんはリン酸を多く含むのが特徴で、花や果物の着色・糖度アップに有効とされています。即効性が高い反面、濃度が強いため、生のまま施すと作物の根を傷めるリスクがあります。
鶏ふん堆肥を使う際は、しっかり完熟させるのはもちろん、使用量を守ることが大切です。特に窒素分が多い分、花や果実を実らせる時期には適量の追肥として利用できます。過剰に施用すると、徒長や病害リスクが高まるため注意しましょう。
馬ふん
馬ふんは草食動物特有の繊維質が多く、牛ふんに比べてやや粒状でかさばりやすいのが特徴です。一般的には牛ふんよりもやや窒素分が少ない傾向にありますが、その分、土壌に入れるとゆっくりと分解が進み、徐々に栄養を放出します。
発酵時に高温を得やすいため、堆肥化の過程で雑菌や害虫を減らし、安全性を高めることが可能です。大型の牧場や乗馬クラブで入手できる場合が多く、堆肥化が進んだ馬ふんは、花壇や畑などさまざまな場所で重宝されます。
堆肥の役割・効果

堆肥は土壌に必要な栄養素を補いつつ、土壌環境を最適化する万能選手ともいえます。
作物の根がしっかり張り、健全に成長できる土台をつくるだけでなく、微生物やミミズなどの土壌生物が棲みやすい環境を整える役割も担います。
多様な素材を活用する堆肥は、単一成分の肥料に比べて複合的な効果が期待できるのが強みです。特に有機成分が土壌の団粒構造を形成し、保水力や排水性を高め、作物の生育に理想的な条件を作り出します。
さらに、微生物が有害菌を抑制する効果も見込めるため、環境に優しい作物栽培を目指すなら堆肥は欠かせない存在です。
肥料としての効果・効能
堆肥は窒素・リン酸・カリなどを含んでおり、化学肥料ほどの即効性はないものの、作物の生育に十分な栄養を長期間にわたって緩やかに供給します。
そのため、作物の根や茎、実がバランスよく育ち、品質の高い収穫物が期待できます。特に果菜類や果樹などの実もの作物では、甘味や旨味の向上につながるケースが多いです。
持続的に施用することで土壌中の有機物量が増し、化学肥料に頼らなくても作物をしっかり育てられる環境を整える点が大きな利点です。
土壌改良の効果・効能
堆肥に含まれる有機物は土の粘土粒子と結合して「団粒構造」を形成し、通気性や保水性を同時に高めます。これにより、根が呼吸しやすくなり、必要な水分や栄養を吸収しやすい土壌環境が作られます。
また、適度な保肥力が生まれるため、施肥による栄養分の流失を防ぐ効果もあります。加えて、微生物の活動が活発化し、病原菌や有害微生物の増殖を抑える効果が期待できるため、連作障害の予防にもつながります。
結果的に化学薬品の使用頻度が減り、環境負荷を軽減できる点も見逃せません。
関連記事はこちら
堆肥のメリット・デメリット

堆肥は作物と土壌の双方に多大な恩恵をもたらす一方で、扱い方を誤るとトラブルの原因になることもあります。臭いや虫の発生、過剰施用による塩害など、メリットとデメリットを正しく理解し、状況に応じて上手に活用することが重要です。
特に動物性堆肥は発酵・熟成の度合い次第で品質が大きく変わるため、選ぶ際には信頼できるブランドや生産者を確かめる必要があります。以下でメリット・デメリットを整理し、堆肥との上手な付き合い方を探ります。
[メリット]
- 土壌改良:保水性・排水性を改善し、根が健やかに育つ土壌を形成。
- 緩やかな肥料効果:土壌に優しい形で栄養供給し、長期的に土を肥沃にする。
- 生態系の活性化:微生物やミミズなど土壌生物を増やし、病害虫の抑制にも貢献。
- 環境保全:生ごみや家畜排せつ物を再資源化し、廃棄物の減量やCO₂排出量の削減につながる。
[デメリット]
- 発酵管理が必要:適切に発酵させないと、においや害虫の発生源になる可能性がある。
- 塩分過多のリスク:過剰施用は土壌の塩類濃度を上昇させ、作物の根を傷める恐れ。
- 作り方・保存場所の確保:自家製で作る場合、切り返しや温度管理など手間がかかり、保管スペースも必要。
- 即効性は低め:化学肥料に比べて作物への効果が出るまで時間がかかる。
堆肥の使い方

堆肥を活かすためには、適切な時期と方法で施用することが大切です。作り方だけでなく、施用のタイミングや施用量を間違えると、思ったような効果が得られないばかりか、逆効果になる場合もあります。
たとえば、未熟な堆肥を施すと土壌中の窒素が微生物に吸収され、作物の成長を妨げる可能性があります。ここでは、使用時期と散布方法を中心に、堆肥の効率的な使い方を解説します。
[使用時期]
堆肥は作物を植え付ける前や収穫後の土づくりの段階で施用すると、土壌とよく馴染んで効果的です。特に、畑やプランターの準備段階で全体に混ぜ込むことで、微生物が活動する時間を確保し、植え付けまでに土の状態を整えられます。
また、作物の生育期間中でも、表土に薄くまいて軽く耕す「追肥」として使える場合がありますが、その際は堆肥が充分に熟成していることを確認してから施用すると安心です。
[散布方法]
堆肥の散布は、耕うん時に全面へ均一にまく方法、畝間や株元に部分的に施す方法、作物の生育ステージに合わせて追肥する方法などがあります。家庭菜園の場合、スコップで均等にばらまいて耕すだけでも効果は十分。
大型農家では、散布機などを用いて一度に大きな面積をカバーすることも可能です。施用量は土壌診断や作物の種類によって異なるため、目安を確認しながら少しずつ調整します。
過剰施用は塩害や病害リスクを高める原因になるため、徐々に増減を試しながら土壌の状態を観察するのが理想的です。
地域資源を上手に使おう

堆肥づくりは、地域で発生する廃棄物を減らしながら資源を循環させる絶好の機会です。落ち葉やもみ殻、稲わらなど、身近な植物性資源を活用することで化学肥料の使用を抑え、経費節減にもつながります。
地域の畜産農家と連携すれば、牛ふんや鶏ふんなどを効率的に入手し、お互いの生産活動を補完し合えるでしょう。
また、自治体や農協(JA)によっては、堆肥づくりの講習会や資材の共同購入などのサポートを行っているところもあります。こうした取り組みに参加すれば、堆肥の品質向上や情報交換が進み、地域全体の農業レベルがアップするメリットも得られます。
まとめ
堆肥は土づくりの基盤を支え、作物の品質や収量を高めるだけでなく、環境保護や廃棄物削減にも貢献する重要な資材です。
植物性堆肥と動物性堆肥を上手に使い分けることで、栄養バランスのとれた土壌を実現し、長期的な土壌改良効果が得られます。即効性は低いものの、ゆっくりと土壌環境を改善し、連作障害の防止や病害虫の抑制といった副次的メリットももたらします。
自家製から市販品までさまざまな形で入手可能なので、目的や作物に合わせた選択が可能です。正しい発酵管理と施用方法を心がけながら、地域資源を有効活用して、持続的で豊かな農業・園芸をぜひ実践してみてください。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。
\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/
LINE登録で「肥料パンフレット」&
「お悩み解決シート」進呈中!
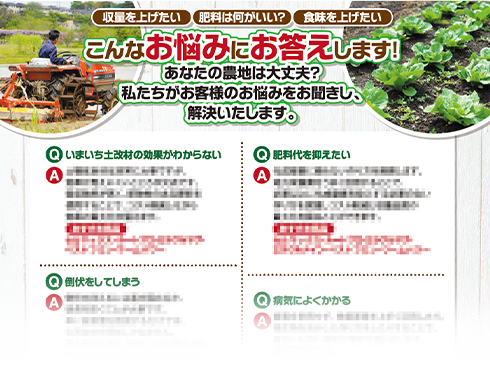
「どの肥料を使えばいいかわからない」
「生育がイマイチだけど、原因が見えない」
そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!
プレゼント内容
- 肥料の選び方がわかるパンフレット
- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」
LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!