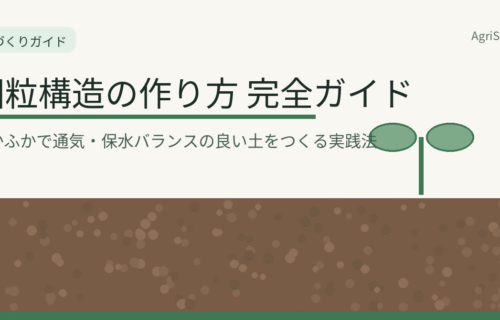台風や集中豪雨などの激しい風雨にさらされると、稲や麦といった背丈の高い作物は大きなリスクを抱えます。そのリスクこそ「倒伏」。一度倒伏が発生すれば、収量だけでなく作物の品質にも深刻な影響が及び、農業経営に大きなダメージを与えかねません。
そこで注目を集めているのが、「倒伏軽減剤」として活用できる肥料です。肥料は単に作物を育てるための栄養源にとどまらず、茎や根をしっかり強化し、外的ストレスに耐えられる体質をつくる上で欠かせない存在となります。
本記事では、倒伏を防ぐために押さえておきたい肥料の基礎知識から、具体的な種類や施用方法、実際の活用事例までを幅広く解説します。倒伏を回避しながら、安定した収量と高品質を目指すためのヒントをぜひ最後までご覧ください。
倒伏軽減剤としての肥料の基本知識

肥料による倒伏防止のメカニズム
作物が倒伏しやすくなる要因の一つは、茎や根の強度が十分でないことです。適切な肥料を与えることで、これらの強度を高められる点が倒伏防止の大きなポイントとなります。
具体的には、細胞を形成・強化するカルシウムや、イネ科の茎をしなやかに且つ頑丈にするケイ酸が重要です。また、十分なカリを施用することで、作物の水分調節能力が向上し、茎葉の健全な発育をサポートします。
一方で、窒素成分を過剰に投与すると徒長(背が過度に伸びる)を引き起こし、結果的に茎が軟弱化して倒伏リスクが高まることがあります。こうしたメカニズムを理解することで、作物を倒伏から守るための施肥設計が可能となります。
土壌バランスと作物の健康
倒伏を未然に防ぐには、土壌環境そのものを健全に保つことも欠かせません。土壌pHが極端に酸性・アルカリ性に偏っていると、必要な栄養素の吸収効率が下がり、作物の根張りや茎の強度に影響を及ぼします。
また、土壌の物理性(通気性や排水性)が悪いと根が十分に発達せず、少しの風雨でも倒伏しやすい株になりがちです。適度な有機質の投入や土壌改良剤の活用で団粒構造を形成し、作物が強く根を張れる環境を整えることが重要です。
健全な土壌は微生物の活動も活発になり、結果として倒伏防止につながる作物の健康な生育を助けます。
ケイ酸・カルシウムなど作物を強化する主要成分
ケイ酸(シリカ)はイネ科作物の茎細胞を強化する働きがあり、水稲や小麦などにとって重要な倒伏対策成分です。
また、カルシウムは細胞壁を硬くする役割を担い、茎だけでなく果実や根の形成にも良い影響を及ぼします。苦土(マグネシウム)は光合成に必須のクロロフィルの構成要素であり、強健な作物づくりに不可欠です。これらの成分をバランス良く補うことで、風雨や台風などの外的ストレスにも耐えうる作物体質を育てることが可能になります。
ただし、すべてを過剰に与えれば良いわけではなく、土壌診断や作物の生育ステージに合わせて必要量を的確に施用することがポイントです。
倒伏軽減剤としてふさわしい肥料の種類

ケイ酸肥料(ケイ酸塩肥料)の特徴と効果
ケイ酸肥料は稲作をはじめとするイネ科作物の倒伏防止に広く利用されており、稈(茎)を強化して風雨に耐えやすくします。ケイ酸は土壌中でも比較的ゆっくり溶出するため、長期的な作物の体質改善に役立ちます。
また、光合成効率の向上や病害抵抗性の強化にも関わるとされ、収量や品質面の向上が期待できる点が魅力です。
施用量は土壌中のケイ酸含有量や作物の需要量を考慮しながら決定するのが望ましく、過剰施用による効果の飽和や土壌バランスの崩れには注意が必要です。
関連記事はこちら
ケイ酸で稲を守る!倒伏&高温障害を防ぐ効果と肥料の使い方を徹底解説
カリウム肥料の特徴と効果
カリウムは主に作物の浸透圧調整や水分吸収に関わり、作物の丈夫さを左右する栄養素です。カリウム肥料を適切に施用することで、茎がしっかりと伸び、根の成長も促されるため、倒伏リスクを抑制できます。
さらに、カリウムは糖分の合成にも関与するため、果菜類や果樹などでは品質向上の面でもメリットがあります。
ただし、カリウムが多すぎると他の要素(特にマグネシウムやカルシウム)の吸収を阻害する場合があるため、土壌診断の結果を参考にしたバランスの良い施用が重要です。
関連記事はこちら
石灰・苦土系肥料の特徴と倒伏軽減への影響
石灰資材は土壌pHを中性付近に近づける働きがあり、酸性土壌で育てる場合に特に効果を発揮します。カルシウム分は細胞壁の形成・強化を補助し、苦土(マグネシウム)は健全な光合成を維持するために必要な成分です。
これらを与えることで茎や根が強化されるため、倒伏の危険性を下げる効果が期待できます。石灰系肥料にもさまざまな種類があり、即効性の高い消石灰や持続的にpH調整する苦土石灰などを、土壌条件や作物特性に応じて選ぶとよいでしょう。
関連記事はこちら
苦土石灰とは?肥料としての効果・使い方・注意点まで徹底解説!
有機質肥料のメリット・デメリット
家畜ふんや腐葉土などを原料とする有機質肥料は、土壌の団粒構造を育み、保水性や通気性を高める効果があります。微生物の活動を活発化させることで、長期的な土壌改良に寄与し、結果的に強健な根を張れる環境を整えられます。
ただし、栄養成分の放出速度が遅い場合や、成分バランスに偏りがある場合もあるため、即効性を求める作物や短期栽培では注意が必要です。
適切な発酵処理が行われていない有機肥料を使用すると、病原菌の発生リスクや虫害が増す恐れもあるため、安全性や品質を確認することが大切です。
関連記事はこちら
総合肥料・微量要素肥料の使い分け
N(窒素)・P(リン)・K(カリウム)をバランス良く含む総合肥料は、多くの栽培シーンで重宝します。
一方で、微量要素(ボロン、マンガン、亜鉛など)不足が原因で倒伏リスクや品質低下が生じる場合もあり、総合肥料だけでは不十分なケースがあることに留意が必要です。
微量要素肥料は特定の作物や土壌条件で欠乏が顕著な場合に、ピンポイントで補給できるメリットがあります。作物の種類・生育段階・土壌環境を鑑みながら、総合肥料と微量要素肥料を適切に使い分けることで、倒伏しにくい強い作物づくりにつながります。
関連記事はこちら
肥料選びのポイント
作物の種類や土壌診断結果とのマッチング
まず重要なのは、育てたい作物の特性や生育ステージ、そして畑や田んぼの土壌状態を正確に把握することです。
土壌診断を行うことで、pHや有機物量、主要な栄養素の含有量を客観的に確認できます。
たとえば、イネ科作物ならケイ酸を重視し、野菜作ならカルシウムやマグネシウムを重点的に施用するといった具合に、作物と土壌の状態を組み合わせて最適な肥料を選択することが倒伏予防の近道となります。
肥料成分表示の見方とチェックすべきポイント
市販の肥料には必ず成分表示が記載されています。N-P-Kの三要素だけでなく、カルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)、さらにはケイ酸(Si)などが記載されている場合も多いです。
倒伏対策を目的とするなら、ケイ酸やカルシウムの含有量がどの程度あるかをチェックするとともに、それらが速効性か緩効性かも確認しましょう。また、同じ「石灰肥料」でも成分含有率や溶解速度が異なるため、製品ラベルを細かく読むことで、施用量やタイミングの目安を得られます。
気候・栽培環境に合わせた施用タイミングと施用量
倒伏は、特に作物が背丈を伸ばす時期にリスクが高まります。そのため、元肥として土壌改良を施すのか、作物が茎を伸ばし始めた頃に追肥をするのかによって、最適なタイミングと量が変わります。
豪雨シーズンや台風の多い地域では、あらかじめ茎を強化する成分をしっかり入れておくことが有効です。また、降雨量が多いと肥料分が流出しやすいため、追肥を複数回に分けて与える工夫も検討しましょう。
地域や年ごとの気候パターンを掴むことで、より緻密な施肥管理が行えます。
倒伏軽減剤(肥料)の効果的な施用方法

元肥と追肥の使い分け
元肥は土壌そのものの基盤を整える役割が大きく、カルシウムや苦土などを含む土壌改良系の肥料を中心に施用することが多いです。
追肥では、成長ステージや天候状況に応じて、ケイ酸やカリウムなど倒伏抑制に特化した要素を追加します。元肥だけで十分な栄養を確保しようとすると、過剰な施用につながりやすいため注意が必要です。
分割施肥によって、作物が必要とする時期に必要な成分を補うことで、茎葉の健全な成長をサポートでき、倒伏リスクを低減します。
関連記事はこちら
土壌改良剤との併用で相乗効果を狙う
石灰や苦土石灰、ケイ酸質資材などの土壌改良剤を活用すると、pH調整や団粒構造の形成が促進され、根の張りが良くなるメリットがあります。
特に、水はけや通気性が悪い土壌では、土壌改良剤を入れることで作物の根が健全に発達し、重心を安定させて倒伏を防ぎやすくなります。
有機質改良剤も併用すれば土壌微生物が活性化し、長期的に地力が向上する効果が期待できます。ただし、改良剤の種類によっては即効性が低かったり、施用量の目安が異なるため、事前に確認して計画的に施用しましょう。
その他の倒伏対策(支柱設置など)との組み合わせ
肥料を活用した倒伏対策だけでなく、物理的な支柱設置やネット張りなどを併用することも有効です。台風や強風が多い地域では、作物が一定以上の高さになる前に支柱を立て、複数の株を連結させる方法も検討されます。
こうした方法を肥料施用と組み合わせることで、根や茎を強化しつつ、外的要因による倒伏リスクをさらに低減できます。また、水管理(潅水や排水)を適切に行うことも、作物の姿勢保持に大きく影響します。
総合的な倒伏対策を実施することで、安定した収量と品質を確保しやすくなります。
実際の活用事例
水稲の倒伏対策における肥料選択
水稲では、出穂前後の時期に茎が急激に伸長し、台風や大雨で倒伏しやすくなります。そこでケイ酸質肥料を生育初期から施用し、茎を太くすることで稲体を強化しておく手法が一般的です。
加えて、カリウム成分の不足は稲の健全な茎葉形成を妨げるため、土壌診断でカリウムが不足している場合は早めに補うのが得策です。また、稲刈り時期を考慮しながら、追肥のタイミングを調整することも倒伏を回避しつつ高収量を狙うカギとなります。
関連記事はこちら
倒伏を防ぐ稲作の秘訣!高収量&高品質の具体策
稲が倒伏したら?今すぐできる対策と予防ポイント
小麦・大麦の倒伏軽減への応用
小麦や大麦などイネ科の穀物でも、倒伏は収量や品質に直結する重大な問題です。石灰や苦土資材で土壌pHを整えると同時に、必要に応じてケイ酸肥料を補給しておくと、茎や節間が強化されやすくなります。
さらに、適切なカリウムと窒素のバランスを保つことが大切です。過剰な窒素で徒長が進めば一気に倒伏の危険性が高まるため、追肥のタイミングを工夫し、風雨の多い時期までに茎をしっかりと仕上げる施肥設計を心がけましょう。
野菜作(トマト・ナスなど)の事例
トマトやナスなど、支柱が必須の野菜でも、茎の太さや根の張りを強化しておくと、収穫作業がスムーズになり、病害リスクも下がるとされています。
カルシウムとカリウムが不足すると実が肥大しにくかったり、尻腐れ病の原因にもなり得るため、必須成分を適切に補給することがポイントです。
また、ケイ酸肥料を適度に与えることで植物体を丈夫にし、台風時などの風で株が折れるリスクを軽減できます。支柱との併用で倒伏を最小限に抑えつつ、生育後半まで安定した収量を確保できる事例も報告されています。
倒伏軽減剤のおすすめ:高吸収型ケイ酸資材「セルマックス」

稲作において倒伏は収量と品質に大きな影響を与える重要な課題です。従来のケイ酸資材では「効きにくい」「土壌条件によって反応が遅い」といった問題がありましたが、そんな課題を解決する画期的な倒伏軽減剤として「セルマックス」をご紹介します。
セルマックスの特徴
セルマックスは、独自のマイクロカプセル技術により、ケイ酸とカルシウムを作物が吸収しやすい形で配合した液体タイプの高吸収型ケイ酸資材です。 圃場に投入後すぐに効果を発揮し、一般的なケイカルや珪酸苦土石灰と比較して、速効性と安定性の両方を実現しています。
倒伏軽減における主なメリット
- 速効性: 投入後すぐに作物が吸収できる形で設計されているため、短期間で茎の強化効果が期待できます
- 総合強化: ケイ酸だけでなくカルシウムも同時に補給することで、根・茎・葉の総合的な強化が可能です
- 施用の簡便性: 水口からの流し込み、葉面散布、ドローン施用など、様々な方法に対応しています
- 経済性: 1反あたり804円〜の低コスト運用が可能で、費用対効果に優れています
特におすすめのケース
- 倒伏リスクが高い年の予防対策として
- 高温障害が懸念される気象条件下での茎強化対策
- 短期間で確実な効果を求める場合
- 従来のケイ酸資材で満足な結果が得られなかった圃場
導入のポイント
セルマックスの効果を最大限に活用するためには、圃場の状況や栽培ステージに応じた適切な施用タイミングが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、計画的な導入を行うことで、より確実な倒伏軽減効果が期待できます。
倒伏対策でお悩みの稲作現場において、セルマックスは信頼できる選択肢となるでしょう。
まとめ
肥料を活用した倒伏軽減の要点整理
作物の倒伏を防ぐには、茎と根の強化が必須であり、ケイ酸やカルシウム、適度なカリウムなどの施用が効果的です。土壌診断を通じて不足しがちな成分を的確に見極めることで、効率よく倒伏軽減につなげることができます。
また、有機質肥料や土壌改良剤を上手に活用し、土壌の物理性・化学性を整えることも重要です。単に肥料を多く与えるのではなく、バランスを重視する点が成功のカギとなります。
失敗しないための注意点・今後の展望
過剰施肥は逆に作物を軟弱化させ、倒伏しやすい体質をつくる原因になります。窒素肥料の過度な使用や、一度に大量の肥料を施用するのは避けましょう。
作物ごとの特性や気候条件を把握し、適切な時期に分割施肥を行うことで、安定した収穫が望めます。今後は、精密農業や土壌モニタリング技術の進歩により、さらに的確な施肥設計が普及し、倒伏リスクを最小限に抑える取り組みが進むと考えられます。
最適な倒伏軽減剤(肥料)で安定した収量を目指す
最適な倒伏軽減剤(肥料)を選定し、適切な時期と量で施用することで、台風や大雨が多い環境下でも強い作物を育てることが可能です。
安定した収量と高品質な作物の生産は、農業経営のリスクヘッジや収益向上に直結します。ケイ酸・カルシウム・カリウムなどの主成分を中心に、微量要素や有機質のバランスを考慮して施肥設計を行い、総合的な倒伏対策を実践することが成功への道です。
環境に配慮しつつ、強靭な作物体質を目指す取り組みをぜひ進めてみてください。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。
\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/
LINE登録で「肥料パンフレット」&
「お悩み解決シート」進呈中!
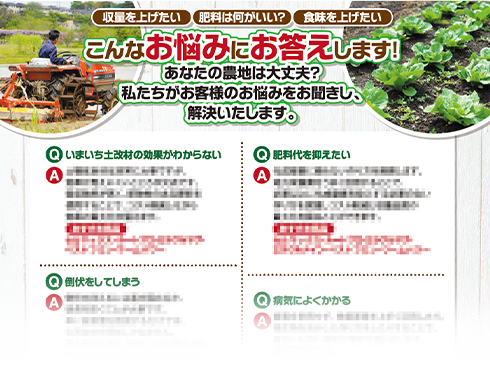
「どの肥料を使えばいいかわからない」
「生育がイマイチだけど、原因が見えない」
そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!
プレゼント内容
- 肥料の選び方がわかるパンフレット
- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」
LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!