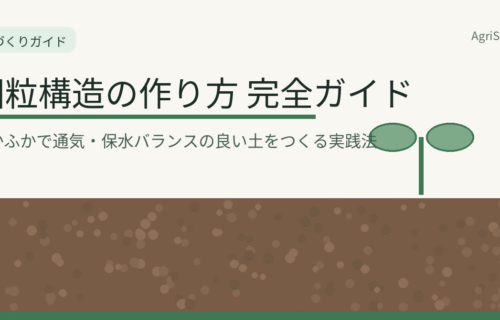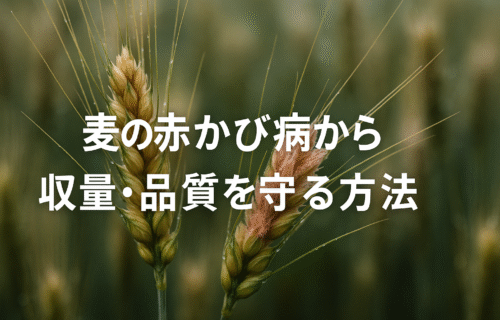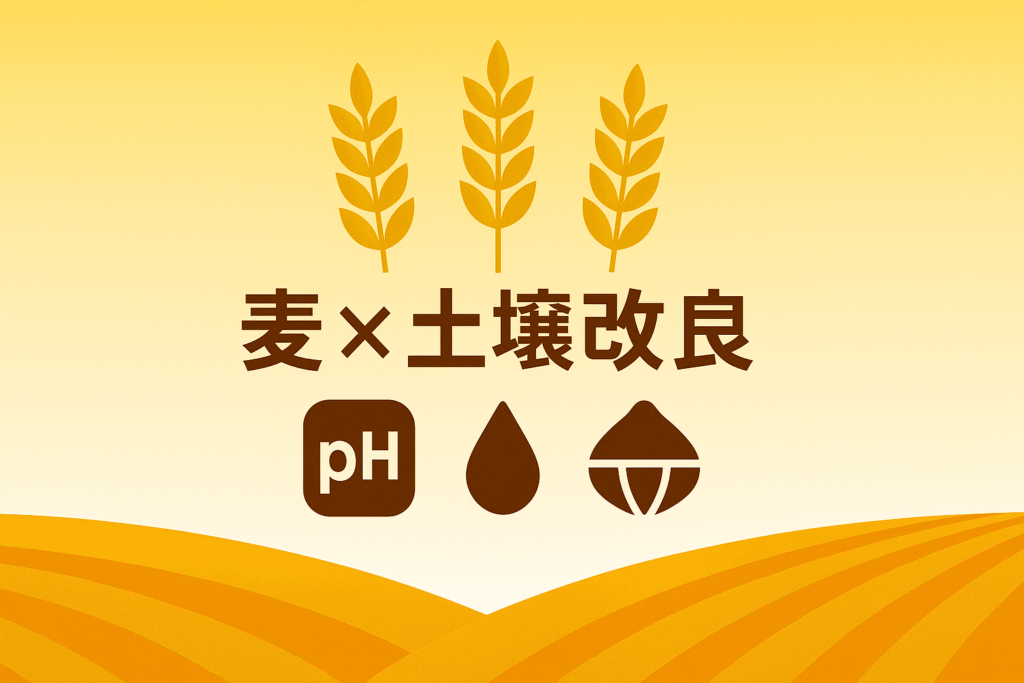
麦栽培で良い収穫を得るために、土づくりはとても大切です。
麦は酸性土壌に弱く、生育障害や極端な場合は発芽障害を起こします。しかし、適切な土壌改良を行うことで、麦の収量と品質を大きく向上させることができます。
日本の多くの畑では、雨の影響で土が酸性になりやすく、また連作により土が固くなったり養分が偏ったりする問題があります。これらの問題を解決するには、pH調整、有機物の投入、土の物理性改善が重要になります。
この記事では、農家の皆さんが実際に取り組みやすい土壌改良の方法を、基礎から実践まで分かりやすく解説します。科学的な裏付けがある方法を中心に、コストを抑えながら効果的に土づくりを進める方法をご紹介していきます。
麦栽培と土壌改良の基礎知識
麦が求める理想的な土壌条件
適正な土壌酸度は小麦でpH6.0~7.5、大麦でpH6.5~8.0程度です。この範囲では、麦に必要な窒素、リン酸、カリウムなどの養分が最も吸収されやすくなります。
麦は水はけが良く、かつ適度に水を保てる土を好みます。べちゃべちゃに湿った土では根腐れを起こし、逆にカラカラに乾いた土では水分不足になってしまいます。理想的なのは、雨の後に水がたまらず、でも乾燥しすぎない土です。
また、土に2~3%程度の有機物(腐葉土や堆肥由来)があると、土がふかふかになって麦の根が伸びやすくなります。堆厩肥などの有機物の施用は、土壌の通気性や透水性を改良して根の伸長を促し、麦の健全な発育を進めます。
土壌改良が麦の収量に与える影響
適切な土壌改良により、麦の収量は20~40%向上することが分かっています。苦土石灰、消石灰、炭酸石灰等の石灰質肥料を施用し、酸度を調整することで、酸性土壌を改善できます。
播種前に堆肥を施用して、微量要素の補給だけでなく、有機物を補給することで、土壌の保肥力や物理性を改善するようにします。これにより、肥料の効きが良くなり、麦の生育が安定します。
水はけの改善も重要で、湿害を防ぐことで根の病気を減らし、健全な根の発達を促進します。特に梅雨時期の長雨による被害を防ぎ、麦の品質向上にもつながります。
麦栽培でよくある土壌トラブル
最も多い問題は土の酸性化です。雨が多いため、土中のアルカリ分(石灰分)が流される上に、作物が根から養分を吸収すると、かわりに根から水素イオンを出します。水素イオンが出る = pHが下がる(水素イオン濃度が増える) = 酸性に傾くため、日本の土壌は自然に酸性化が進みます。
水はけの悪さも深刻な問題です。特に粘土質の土壌では、雨の後に水がたまりやすく、麦の根が酸素不足になって根腐れを起こします。また、湿った状態が続くと病気の原因となる菌が増えやすくなります。
養分バランスの偏りもよく見られます。窒素が多すぎると麦が軟弱になって倒れやすくなり、リン酸不足では分げつ(茎の数)が少なくなります。連作により特定の養分が不足したり、有害物質がたまったりすることもあります。
麦栽培前の土壌診断と分析方法
土壌pH測定の重要性と適正値
土壌のpH測定は麦栽培で最も基本的で重要な診断です。土壌の中和には数日かかるため、中性にpHが傾いたかどうかは、消石灰では3~5日程度、苦土石灰では7日程度、有機石灰では10日程度を目安に確認することをおすすめします。
pH電極を浸ける方法では、まずは調査する土壌1に対して蒸留水2.5を加え、約30分間撹拌しましょう。そうしてできた上澄み液に、pH電極を浸け軽く混ぜながら30秒後に測定値を読みます。
簡単な方法として、土と水を1対2.5の割合でよく混ぜます。次に上澄み液が透明になるまで数分放置し、水が澄んだ部分にpH試験紙を浸して色見本と照合します。
圃場全体の傾向を把握するため、10a当たり15~20地点からサンプルを採取し、それらを混合して平均値を求めることが大切です。
土壌の物理性チェック(排水性・保水性)
麦栽培では、土の水はけと水持ちのバランスが重要です。簡単な確認方法として、直径10cmほどの筒を土に5cm埋め込み、その中に水を注いで水位の下がる速さを測定します。麦に適した土壌では、1時間に2~5cm程度の速度で水が浸透していきます。
土を手で握って確認する方法もあります。適度な水分の土は、握ると固まりますが、指で押すと崩れる程度が理想的です。握っても固まらない場合は乾燥しすぎ、握ると水が滴る場合は湿りすぎです。
土の硬さも重要で、麦の根がしっかり伸びるには、表層から20cm深までは比較的柔らかく、硬い層がないことが望ましいとされています。硬い層がある場合は、深く耕すことで改善できます。
養分バランスの確認方法
微量要素は、堆肥などを定期的に投入することで、十分に供給されていると考えられます。ただし、土壌のpHが低すぎたり、高すぎたり、塩基のバランスが崩れていると、微量要素をうまく吸収できずに欠乏症となる恐れがあるので、注意します。
土壌分析は、信頼できる分析機関に依頼するか、簡易診断キットを使用して行います。主要な項目には、pH、窒素、リン酸、カリウム、石灰、苦土が含まれます。
JA(農協)では組合員向けに土壌診断サービスを提供している場合が多く、年に1回は、土壌診断をし、自分の畑土の性質を把握しておくことが重要です。少量の土を乾燥後、各支所に提出するだけで診断が可能です。組合員であれば、組合員料金が適用されるか、一部の地域や期間中には無償で診断を受けることが可能です。
麦に最適な土壌改良資材と選び方
有機質資材(堆肥・腐葉土・緑肥)
牛糞堆肥には、窒素・リン酸・カリウム・カルシウム・マグネシウムなどの主要栄養素をはじめ、鉄・マンガン・銅・亜鉛・モリブデン・ホウ素などの微量要素が含まれており、作物に対する総合的な栄養の供給源となります。
牛糞堆肥は最も一般的で、含まれる窒素の多くは、施用後長期にわたってゆっくりと肥効が現れるという傾向があります。施用量は10a当たり2~3トンが標準的で、播種の1~2ヶ月前に施用します。
完熟堆肥とは、有機物が微生物の作用によって分解され、十分に腐熟化した状態の堆肥のことです。牛糞堆肥のデメリットの多くは、未熟な堆肥を施用した場合に発生しやすくなります。そのため、第一に完熟堆肥を選ぶことが大切です。
緑肥作物では、緑肥とは緑の肥料と書く通り、新鮮な緑色の植物そのものを土壌にすき込み使用する肥料のことを指します。麦の前作として、ヘアリーベッチやクローバーなどのマメ科植物を栽培することで、土壌への窒素供給と有機物補給を同時に行うことができます。
無機質資材(石灰・ゼオライト・パーライト)
苦土石灰は、カルシウム(石灰)とマグネシウム(苦土)を含む天然のドロマイト鉱石を粉砕してつくられた、土壌のpH調整資材です。石灰と苦土をバランスよく含むため、カルシウムだけを過剰に与える心配がなく、野菜の苦土欠乏を防ぐのにも効果的です。
消石灰は速効性があることも特徴の一つです。また殺菌力もあるため、防除用資材としても使われますが、苦土石灰は緩効性のため、散布から効果が表れるまで1~2週間かかります。
1平方mあたり100g(1pH上げる場合、1平方mあたり150~200g)を目安に散布し、よく土を混ぜます。石灰と肥料を同時に使用すると作物の内部にある酸素を奪うアンモニアガスが発生してしまうため、肥料の投入は石灰をまいてから1〜2週間後に行いましょう。
ゼオライトは、肥料成分の保持と緩やかな供給に効果があります。特に、砂っぽい土壌の保肥力向上に有効で、10a当たり300~500kgの施用により、肥料の流出を防げます。
微生物資材の活用法
有用微生物群(EM菌)は、土壌の有機物分解促進と病原菌の抑制効果があります。播種前に10a当たり20~30リットルを希釈して土壌に散布し、有機質資材と組み合わせることで相乗効果が期待できます。
菌根菌資材は、麦の根系と共生することで、リン酸の吸収効率を大きく向上させます。特に、リン酸を固定しやすい火山灰土壌では、菌根菌の接種により、リン酸肥料の使用量を30~50%削減できる場合があります。
これらの微生物資材は、化学農薬との併用を避け、有機質資材と組み合わせることで、その効果を最大限に引き出すことができます。
麦栽培における実践的土壌改良手順
播種前の土作り(秋播き麦の場合)
秋播き麦の土作りは、8月下旬から9月上旬にかけて開始します。まず、前作物の残渣を適切に処理し、病気や害虫の越冬場所を除去します。堆厩肥が手に入りにくい場合は、稲わらでも効果があります。
土壌診断結果に基づき、pH調整用の石灰質資材を施用します。苦土石灰を土壌に用いることで、主に2つの効果が期待されます。それは、pHの調整と養分の補給です。播種の3~4週間前に施用することで、土壌との十分な反応時間を確保できます。
堆厩肥や稲わらはプラウで深耕し、深く鋤込む方が効果的です。深耕によって作土層直下の耕盤層が破砕されるため透水性や通気性が良くなり、湿害も抑えられます。
春播き麦の土壌改良タイミング
春播き麦の土壌改良は、融雪後の土壌が適度に乾燥した3月中旬から4月上旬に実施します。冬の凍結と融解により土壌構造が変化している場合があるため、まず土壌の状態を確認します。
春播き麦では、播種から収穫までの期間が短いため、即効性のある土壌改良が重要です。石灰質資材は、播種の2週間前までに施用し、有機質資材は完熟したものを選択します。
春の降雨により肥料成分が流れ出すリスクが高いため、緩効性肥料や被覆肥料の使用を検討します。播種床の準備は、地温が5℃以上安定した時点で行い、麦の発芽に適した環境を整えます。
改良資材の施用量と混合方法
アレニウス表は、土壌改良に広く用いられている表であり、ph6.5にする場合の目安となる炭酸カルシウムの必要量が記載されています。一般的に、pH1ポイント上昇させるには、軽い土で100kg/10a、普通の土で150kg/10a、重い土で200kg/10aの炭酸カルシウム相当量が必要です。
有機質資材の施用量は、土壌の有機物含量と目標値から算出します。有機物含量を1%向上させるには、約3~4トン/10aの完熟堆肥が必要とされています。ただし、一度に大量施用すると養分バランスが崩れる可能性があるため、年間2~3トン/10aを継続的に施用することが推奨されます。
適切な量を畑の表面に均一にまきます。施用量に偏りがあると、作物への効果にばらつきが出てしまいます。苦土石灰をまいたら、土と十分に混ぜ合わせます。石灰はそのままにしておくと雨など水に濡れて固まり、土が硬くなってしまいます。
麦の生育段階別土壌管理
発芽・出芽期の土壌管理
麦の発芽・出芽期は、土壌管理の最も重要な時期の一つです。この段階では、土壌温度と水分管理が発芽率に直接影響します。秋播き麦では、播種後の土壌温度が15~20℃で安定していることが理想的で、この温度範囲では7~10日で発芽が完了します。
播種後の鎮圧は、種子と土壌の密着を良くし、水分の上昇を促進するため重要です。ただし、強すぎる鎮圧は出芽を妨げるため、軽く表面を均す程度に留めます。特に、粘土質土壌では、降雨後の土壌表面の硬化に注意が必要です。
発芽期間中の養分管理では、リン酸の早期供給が重要です。リン酸は麦の根系発達に不可欠で、発芽時に不足すると初期生育が大幅に遅れます。種子の近くにリン酸質肥料を配置する側条施肥は、初期生育促進に極めて効果的です。
分げつ期の追肥と土壌ケア
気温の低い条件下の期間が長い小麦は、春作物や夏作物に比べて、肥切れを起こしやすい作物です。そのため、基肥だけでは満足のいく収量や品質が確保できない場合もあります。
麦の分げつ期は、最終的な収量を決定する重要な生育段階で、適切な追肥と土壌管理により分げつ数を最大化します。分げつ期の追肥は、主茎から3~4葉展開した時期に行い、窒素成分として10a当たり4~6kgを施用します。
土壌の物理性管理では、分げつ期の中耕除草が重要な作業となります。中耕により土壌の通気性が改善され、根圏への酸素供給が促進されます。ただし、深すぎる中耕は根系を損傷するため、3~5cm程度の浅い中耕に留めます。
穂孕み期〜成熟期の水分管理
穂孕み期から成熟期にかけての水分管理は、麦の品質と収量に大きな影響を与えます。穂孕み期は、麦の水分要求量が最も高い時期で、この時期の水分不足は実らない粒の増加と粒重の減少を招きます。
開花期以降の水分管理では、適度な水分ストレスが品質向上に効果的です。登熟期に入ると、過度の水分供給は病害の発生を助長し、粒の充実を阻害します。収穫前2~3週間は、適度な乾燥状態を維持します。
成熟期の土壌管理では、収穫作業に適した圃場条件の確保が重要です。収穫前の過度の降雨は、土壌を軟らかくし、機械作業の効率を低下させます。必要に応じて、排水溝の設置や一時的な排水対策により、圃場の乾燥を促進します。
麦栽培で効果的な土壌改良テクニック
輪作による土壌改善効果
輪作は、麦栽培において最も効果的で持続可能な土壌改良手法の一つです。麦類を含む4年輪作(麦→大豆→トウモロコシ→麦)では、土壌の養分バランスが自然に調整され、病害虫の発生も抑制されます。
緑肥に含まれる養分は、マメ科の根粒の窒素固定に由来するものか、土壌から吸収されたものです。窒素固定の場合、田畑の外からの窒素が富化されることになります。大豆などのマメ科作物は、根粒菌による窒素固定により土壌の窒素供給力を向上させます。
根系特性の異なる作物を組み合わせることで、土壌の物理性も改善されます。深い根を持つ作物を輪作に組み込むことで、下層土の硬い層を生物学的に破砕し、下層土の通気性と透水性を向上させます。
緑肥作物を活用した土作り
緑肥をすき込むことで、作土に多くの有機物が供給されます。緑肥は堆肥よりも分解しやすいですが、1年後に作土に残る有機物の量から考えると、例えば、草丈220 cm、地上部乾物重1.3 t/10a のソルガムでも相当な有機物供給効果があります。
麦の前作として栽培されるヘアリーベッチは、10a当たり100~150kgの窒素を土壌に固定し、後作の麦に対する窒素肥料として機能します。播種は8月下旬から9月上旬に行い、翌春の麦播種前に鋤き込みます。
すき込まれた有機物によって土壌中の微生物が増殖し、その中の有用微生物が次の作物への養分供給を増やすのに役立っていることもあります。緑肥の鋤き込み量は、生重で3~5トン/10aが標準的です。
不耕起栽培での土壌改良
不耕起栽培は、土壌構造を保持しながら麦を栽培する環境保全型農法で、土壌の物理性改善に革新的な効果をもたらします。従来の耕起栽培では、機械による土壌攪拌により、土壌の団粒構造が破壊される場合があります。
不耕起栽培における土壌改良の中心は、表面被覆(マルチング)と有機物の表面施用です。前作物の残渣や藁類を土壌表面に残すことで、土壌侵食の防止、水分保持、土壌温度の安定化が図られます。
土壌生物の活動活性化も不耕起栽培の重要な効果です。ミミズや土壌節足動物の活動により、自然な孔隙システムが形成され、土壌の通気性と透水性が向上します。不耕起栽培への移行には3~5年の期間が必要ですが、確立後は化学肥料の削減と土壌肥沃度の向上が同時に実現されます。
土壌タイプ別の麦栽培対策
粘土質土壌での改良ポイント
粘土質土壌での麦栽培では、排水改良が最重要課題となります。粘土含量が多い重い土では、降雨後の水たまりにより根腐れが発生しやすく、麦の初期生育が著しく阻害されます。
物理的改良として、砂や籾殻、パーライトなどの軽い資材を10a当たり3~5㎥施用し、土壌の水の通りを良くします。また、有機物の継続的施用により、土壌の団粒化を促進し、自然な排水路を形成します。
暗渠排水の設置は、粘土質土壌では特に効果的です。15~20m間隔で深さ60~80cmの暗渠を設置し、過剰な地下水を効率的に排除します。心土破砕も重要な改良手法で、30~40cm深の硬い層をサブソイラーで破砕することにより、下層への排水を促進します。
砂質土壌の保水力向上方法
砂質土壌での麦栽培では、保水力不足による干ばつ害が主要な問題となります。砂が多い土では、降雨後の急速な水分減少により、麦の生育が不安定になります。
保水力向上の基本は、有機物の大量投入です。完熟堆肥を年間3~4トン/10a継続施用することで、土壌の有機物含量を3~4%まで向上させ、保水力を大幅に改善できます。
粘土質資材の混合も効果的な改良方法です。ベントナイトやバーミキュライトを10a当たり500~1000kg施用することで、土壌の保水力と保肥力を同時に向上させます。また、稲わらや麦わらを10a当たり500~800kg被覆することで、土壌表面からの水分蒸発を30~50%削減できます。
酸性土壌の中和と改善策
土壌がアルカリ性になるのは、石灰のやりすぎが原因と考えられますが、日本では逆に酸性土壌の問題の方が一般的です。pH5.5以下の強酸性土壌では、アルミニウムの溶出により根系発達が阻害され、養分吸収能力が著しく低下します。
石灰質資材による中和処理は、土壌診断に基づいて適正量を算出し、播種の4~6週間前に施用します。消石灰は即効性がありますが、過剰施用により急激なpH上昇を招くため、炭酸カルシウムや苦土石灰の使用が安全です。
酸性をアルカリ性に戻すのは簡単ですが、逆にアルカリ性を酸性にするのは難しいため、石灰の撒き過ぎには注意する必要があります。
麦の土壌改良でよくある失敗と対策
過剰施用による弊害
土壌改良資材の過剰施用は、麦栽培において深刻な生育障害を引き起こす原因となります。石灰質資材の過剰施用により土壌pHが8.0以上になると、鉄、マンガン、亜鉛などの微量要素が溶けにくくなり、麦に微量要素欠乏症状が現れます。
石灰資材は、堆肥や肥料と同時に入れないのが基本です。反応が強すぎると、アンモニアが揮発したり、根に悪影響が出ることがあります。適正な施用量を守り、年間の施用量を複数回に分けることで、急激なpH変化を防ぎます。
有機質資材の過剰施用では、未熟堆肥による窒素不足や、塩類濃度障害が発生します。C/N比の高い未熟堆肥は、分解過程で大量の窒素を消費するため、土壌中の使える窒素が一時的に不足し、麦の生育が停滞します。鶏糞堆肥の過剰施用では、塩害により根系の発達が阻害されます。
改良効果が出ない原因
土壌改良の効果が現れない主な原因は、改良資材の選択ミスと施用方法の不適切さです。例えば、水はけの悪い粘土質土壌に対して、保水性資材を施用しても問題は解決されません。土壌の問題点を正確に診断し、それに対応した適切な資材を選択することが不可欠です。
施用方法の不備も効果不発の大きな要因です。表面に散布するだけで土壌との混和が不十分な場合、改良効果は表層に限定され、麦の根系全体には効果が及びません。特に、石灰質資材は土壌との十分な接触が必要で、深さ15~20cmまで均一に混和することが重要です。
土壌の物理的条件も改良効果に影響します。極端に乾燥した土壌や、逆に過湿状態の土壌では、微生物活動が低下し、有機質資材の分解が進みません。適切な土壌水分条件下で改良作業を行い、微生物活動を促進する環境を整えることが重要です。
コストを抑えた効率的改良法
経済的制約がある中でも効果的な土壌改良を実現するには、地域資源の活用と複合的効果を狙った改良法が有効です。稲わらや麦わらなどの農業副産物は、適切な処理により優良な土壌改良資材となります。稲わらは裁断後に窒素質肥料を少量添加して堆積し、3~6ヶ月発酵させることで、良質な有機質資材に変換できます。
肥料の価格高騰が起こり農業経営を圧迫させている中、有機物を施肥する方法の中でも労力やコストでも負担の少ない緑肥を活用する栽培方法に注目が集まっています。ヘアリーベッチなどのマメ科緑肥は、種子代のみで窒素固定と有機物供給を同時に行い、化学肥料費を年間30~50%削減できます。
地域の畜産農家との連携により、堆肥を安価で入手することも有効です。運搬費を削減するため、近隣農家との共同購入や交換作業を組織化します。土壌診断により最も必要な改良項目を特定し、優先順位をつけて段階的に改良を進めることが、コスト効率の向上につながります。
有機栽培における麦の土壌改良
化学肥料を使わない土作り
有機栽培での麦の土作りは、化学肥料に依存しない持続可能な養分供給システムの構築が基本となります。土壌の生物活性を最大限に活用し、有機物の循環により必要な養分を供給します。基本となるのは、完熟堆肥を年間3~4トン/10a施用する有機物ベースの土作りです。
植物性有機質資材も重要な養分源となります。米ぬかは窒素とリン酸を豊富に含み、分解速度が速いため、麦の初期生育促進に効果的です。施用量は10a当たり100~200kgで、播種前に土壌と混和します。
ミネラル供給には、天然由来の資材を活用します。海藻粉末は、微量要素を豊富に含み、麦の品質向上に貢献します。岩石粉末(玄武岩粉、花崗岩粉)は、長期間にわたってカリウムやケイ酸を供給し、麦の耐病性向上効果があります。
自家製堆肥の作り方と活用
高品質な自家製堆肥の製造は、有機栽培成功の鍵となります。材料の選定では、C/N比のバランスが重要で、炭素源(稲わら、落葉、おがくず)と窒素源(家畜糞、生ごみ、緑肥)を3:1の割合で混合します。
次に仕込み堆肥の中に空気が十分入るように通気性のある被覆シートで覆います。水分を調整し、適度な通気があれば、堆肥を仕込んで 2 ~ 3 日のうちに 60℃以上の温度に達します。堆肥化期間は家畜ふんのみなら2カ月、作物残渣の混合なら3カ月、木質物の混合なら6カ月が目安です。
完熟堆肥になっている場合、堆肥の色が黒褐色もしくは黒色になります。黄色や黄褐色、褐色程度の場合は、腐熟化が不十分であるといえます。手に取ってみた際に現物の形状をとどめている場合は腐熟化の途中であり、未熟堆肥です。
天然資材による病害虫対策
有機栽培での病害虫対策は、予防を重視した総合的アプローチが基本となります。土壌の健全性向上により植物の自然抵抗力を高め、天然由来の資材を活用して病害虫の発生を抑制します。
ニーム粉末は、天然の忌避成分を含み、アブラムシなどの害虫防除に効果があります。10a当たり5~10kgを月1回散布します。木酢液の希釈散布(100~200倍)は、土壌の殺菌効果と植物の生育促進効果を併せ持ちます。
拮抗微生物の活用が効果的です。トリコデルマ菌やバチルス菌などの有用微生物は、病原菌との競合により土壌病害を抑制します。これらの微生物資材を土壌に施用することで、根圏環境を改善し、立枯病や根腐病の発生を予防します。
麦栽培の土壌改良 年間スケジュール
春夏の土壌準備作業
3月から8月にかけての春夏期は、秋播き麦の土壌準備を行う重要な期間です。3月下旬から4月上旬にかけて、前年度の土壌分析結果を基に、改良計画を立案します。土壌のpH、養分状態、有機物含量を総合的に評価し、必要な資材の種類と施用量を決定します。
5月から7月は、有機質資材の準備期間となります。自家製堆肥の切り返し作業を継続し、秋の施用に向けて完熟堆肥を準備します。また、緑肥作物の播種も重要な作業で、ヘアリーベッチやクリムゾンクローバーを6月下旬から7月上旬に播種し、秋の鋤き込みまで育成します。
8月は、本格的な土壌改良作業の開始時期です。土壌診断に基づいて石灰質資材を施用し、pH調整を開始します。消石灰の場合は播種の4週間前、炭酸カルシウムの場合は3週間前までに施用を完了します。同時に、基肥として有機質資材を施用し、ロータリーで十分に混和します。
秋の播種前土作り
9月は麦播種直前の最終的な土作り期間で、播種床の準備が中心となります。9月上旬には、緑肥作物の鋤き込み作業を実施します。開花期前後の緑肥を15~20cm深で鋤き込み、2~3週間の分解期間を設けます。
9月中旬以降は、播種床の最終整備を行います。ロータリーによる砕土と整地作業により、種子の発芽に適した細かな土壌状態を作ります。土壌の表面は平坦に整地し、播種深度の均一化を図ります。
播種直前には、土壌水分の確認を行います。適正な土壌水分(握って固まるが、指で押すと崩れる程度)であることを確認し、必要に応じて播種時期を調整します。最終的な肥料調整も行い、播種と同時に施用する追肥の準備を完了します。
冬季の土壌養生と管理
11月から2月の冬季期間は、播種済みの麦の土壌管理と、次年度に向けた土壌養生が主要な作業となります。11月下旬から12月上旬は、麦の発芽・出芽状況を確認し、発芽不良箇所の補播を実施します。
12月から1月は、土壌の凍結融解作用を活用した自然の土壌改良期間です。この期間の凍結融解により、土壌の団粒化が促進され、春先の作業性が向上します。ただし、過度の踏圧は土壌構造を破壊するため、圃場への立ち入りは最小限に抑えます。
2月下旬から3月上旬は、春先の作業準備期間となります。土壌の融解状況を確認し、春の追肥や中耕作業の計画を立案します。また、この時期に次年度の土壌改良計画の見直しを行い、必要な資材の発注準備を進めます。
まとめ:持続可能な麦栽培のための土壌改良
麦栽培における土壌改良は、単年度の収量向上だけでなく、長期的な土壌の健康維持を目指すことが重要です。適切なpH管理、有機物の継続的投入、物理性の改善を基本とした総合的な土壌管理により、麦の安定生産と品質向上を同時に実現することができます。
特に重要なのは、土壌診断に基づく科学的なアプローチです。まず自分の畑の状態を正しく知ることで、無駄な資材投入を避け、必要な改良を効率的に行えるでしょう。年に1回は土壌診断を行い、pH、養分状態、有機物含量を確認しましょう。
経済性と環境負荷のバランスを考慮した土壌改良では、地域資源の活用と輪作システムの導入が効果的です。緑肥作物や農業副産物の活用により、外部からの資材購入費用を減らし、持続可能な養分循環システムを構築できます。
今後の麦栽培では、気候変動への適応も重要な課題となります。極端な天候に対応できる強い土壌作りと、水分・養分利用効率の向上により、環境変動に左右されない安定生産システムの確立が求められます。継続的な土壌の観察と改良技術の改善により、次世代に引き継ぐ健全な農地として麦栽培圃場を維持管理していくことが大切です。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。
\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/
LINE登録で「肥料パンフレット」&
「お悩み解決シート」進呈中!
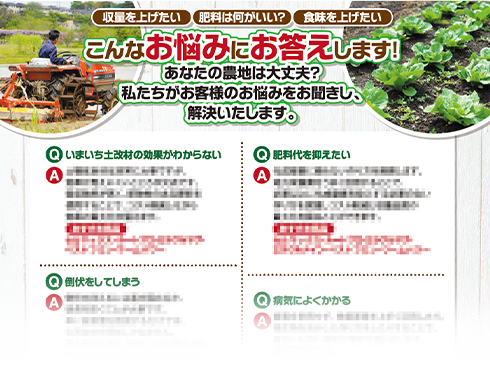
「どの肥料を使えばいいかわからない」
「生育がイマイチだけど、原因が見えない」
そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!
プレゼント内容
- 肥料の選び方がわかるパンフレット
- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」
LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!