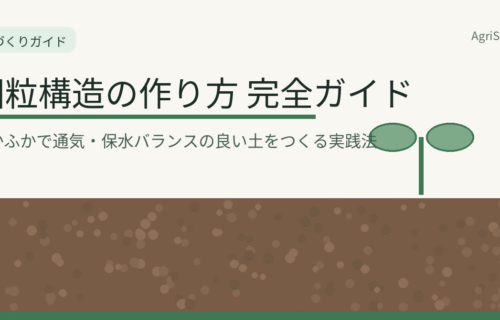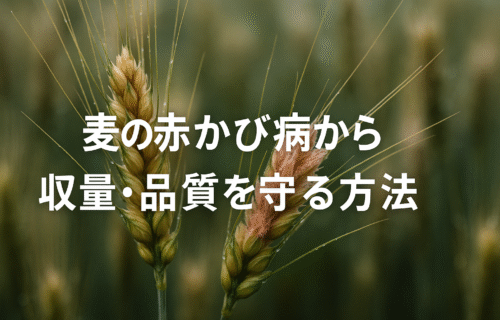麦栽培において、収穫後の乾燥作業は品質を左右する最も重要な工程の一つです。適切な乾燥を行うことで、麦の貯蔵性が向上し、品質劣化を防ぐことができます。また、出荷時期の調整も可能になるため、農家経営にとって欠かせない作業といえるでしょう。
しかし、乾燥方法を間違えると、せっかく育てた麦の品質が大幅に低下してしまう可能性があります。水分が高いまま放置すると変質や異臭が発生し、逆に急激な乾燥を行うと胴割れなどの品質低下を招きます。
この記事では、麦の乾燥に関する基礎知識から実践的な技術まで、農家さんが知っておくべき情報を分かりやすく解説します。機械乾燥と自然乾燥の特徴、適切な温度管理、作業の流れなど、品質の高い麦を生産するための乾燥ノウハウをお伝えします。
麦乾燥の基礎知識
麦乾燥が必要な理由
麦の乾燥は、収穫後の品質維持と長期保存を可能にする重要な作業です。収穫直後の麦は水分量が17〜20%程度と高く、このまま放置すると貯蔵性が著しく悪化します。乾燥により水分を12.5%以下まで下げることで、カビや害虫の発生を防ぎ、安全に貯蔵できるようになります。
また、水分が高いまま製粉を行うと、ふすまと粉の分離がうまくいかず、品質の良い小麦粉を作ることができません。このため、規格を満たす適切な水分まで乾燥することが、高品質な麦を出荷するための必須条件となっています。
さらに、乾燥により出荷時期を調整できるメリットもあります。適切に乾燥・貯蔵された麦は約1年間の保存が可能で、市場価格を見ながら有利な時期に出荷することで、農家収入の向上にもつながります。
麦の種類別乾燥ポイント
麦の種類によって乾燥時の注意点が異なります。小麦の場合は、穀粒温度45℃以下を保ちながら乾燥することが重要です。これより高温になると、タンパク質の変性や澱粉の損傷により、パンや麺の品質に悪影響を与える可能性があります。
ビール大麦は特に注意が必要で、穀粒温度40℃以下に抑える必要があります。これは発芽率を維持するためで、温度が高すぎると麦芽としての価値が失われてしまいます。また、長時間の乾燥は剥皮の原因となるため、適切な時間管理も重要です。
大麦やはだか麦についても、基本的には小麦と同様の温度管理を行いますが、用途に応じて微調整が必要です。食用大麦では食味を重視し、飼料用では効率性を優先するなど、目的に応じた乾燥条件の設定が求められます。
麦乾燥の方法と種類
機械乾燥(主流方式)
現在の麦乾燥では、機械乾燥が主流となっています。特に循環法による大型循環式乾燥機が広く使用されており、効率的で均一な乾燥が可能です。この方式では、麦を乾燥機内で循環させながら熱風を当てることで、ムラなく乾燥させることができます。
循環式乾燥機の仕組みは、投入された麦が複数の層を流れ落ちる間に横から熱風を受けて温められ、その後タンクでテンパリング(温度調整)を行うというサイクルを繰り返すものです。このサイクルにより、麦の表面と内部の水分を均一化し、品質の良い乾燥麦を生産できます。
機械乾燥の最大のメリットは、天候に左右されずに安定した乾燥作業ができることです。また、短時間で大量の麦を処理できるため、作業効率が大幅に向上します。ただし、適切な温度管理と時間設定を行わないと、品質低下を招く可能性があるため、十分な知識と経験が必要です。
自然乾燥(天日干し)
自然乾燥は、刈り取った麦を束ねて稲架(はさ)に掛け、太陽の光と自然の風で乾燥させる伝統的な方法です。この方法では、2〜3週間かけてじっくりと乾燥させるため、麦への負担が少なく、優れた食味を保つことができます。
天日干しの最大の特徴は、昼夜の温度差により麦の味が熟成されることです。また、稲架に吊るすことで養分が穂の部分にゆっくりと移動し、甘みや香りが凝縮されるといわれています。このため、天日干しされた麦は機械乾燥品よりも食味が良いとされ、高値で取引されることが多いです。
ただし、天日干しには手間と時間がかかり、天候に大きく左右されるデメリットがあります。また、鳥害や風による飛散のリスクもあるため、小規模栽培や特別な品質を求める場合に適した方法といえるでしょう。
適切な乾燥条件と管理方法
温度管理の重要性
麦の乾燥において、温度管理は品質を決定する最も重要な要素です。ビール大麦では穀粒温度40℃以下、小麦等では45℃以下を厳守する必要があります。これらの温度を超えると、麦のタンパク質や澱粉が変性し、品質が著しく低下します。
特に初期の水分が高い状態では、低温での乾燥を心がけることが重要です。急激な高温乾燥は麦粒内部の水分移動を阻害し、表面だけが乾燥して内部に水分が残る乾燥ムラ状態を引き起こします。この状態は胴割れの原因となり、精麦時の砕麦率増加につながります。
温度管理のコツは、段階的な昇温です。初期は低温で始め、水分が下がるにつれて徐々に温度を上げることで、効率的かつ品質を保った乾燥が可能になります。また、乾燥機の温度計は定期的に調整、正確な温度管理を行うことが大切です。
乾燥時間と水分調整
麦の乾燥では、水分量を17〜20%から12%前後まで調整する必要があります。この作業には通常、一晩程度の時間をかけて行います。急激な乾燥は品質低下の原因となるため、時間をかけてじっくりと水分を除去することが重要です。
乾燥速度の目安は、毎時0.8%以下の水分減少率を保つことです。これより速い乾燥は麦粒にストレスを与え、胴割れや品質低下を引き起こす可能性があります。特に初期水分が高い場合は、より慎重な乾燥が必要です。
水分ムラを防ぐためには、乾燥前の送風が効果的です。収穫直後の麦は水分ムラが多いため、最初に5〜6時間以上の送風のみを行い、その後熱風を送ることで均一な乾燥が可能になります。また、定期的な水分測定により、乾燥の進行状況を確認することも大切です。
乾燥タイミング
麦の乾燥は、収穫後できるだけ早く開始することが重要です。理想的には収穫後2〜4時間以内に乾燥機に投入し、乾燥を開始します。これより長時間放置すると、熱損粒や異臭麦が発生し、品質が大幅に低下します。
特に梅雨時期の収穫では、高温多湿の環境下で麦の変質が急速に進むため、より迅速な対応が求められます。収穫作業と乾燥作業のスケジュールを事前に調整し、スムーズな流れを確保することが重要です。
気候条件への対応も大切です。湿度が高い日は乾燥時間が長くなる傾向があるため、燃料の準備や作業計画に余裕を持たせることが必要です。また、雨天時の収穫物は水分が高くなるため、より慎重な乾燥管理が求められます。
乾燥作業の実際の流れ
乾燥前の準備作業
乾燥作業を開始する前に、乾燥機の清掃と点検を徹底的に行います。特に穀物乾燥機は水稲と共用されることが多いため、他の穀物の混入を防ぐための清掃が重要です。風洞の端や角落部に穎(えい)などが溜まりやすいので、エアブローなどで除去します。
異種穀粒や異物の混入チェックも欠かせません。これらが混入すると品質低下の原因となるため、混入物が多い場合は別に乾燥させることで、全体の品質維持を図ります。また、乾燥機の安全装置や温度計の動作確認も、事故防止のために必要な作業です。
収穫物の品質チェックも重要な準備作業の一つです。赤かび病などの被害粒がある場合は、事前に仕分けを行い、別途乾燥調製することで、全体への影響を最小限に抑えることができます。このような準備作業により、高品質な乾燥麦の生産が可能になります。
乾燥作業の手順
乾燥機への麦の投入から完了までの手順は、まず麦をベルトコンベアで乾燥機に運び、投入します。循環式乾燥機では、投入された麦が自動的に機内を循環し、各層で熱風を受けながら乾燥が進行します。この間、温度と時間の管理が最も重要となります。
循環システムでは、麦が複数の層を流れ落ちる間に熱風を受け、その後テンパリングタンクで温度調整を行うサイクルを繰り返します。このサイクルにより、麦の表面と内部の水分が均一化され、品質の良い乾燥が実現されます。
品質チェックポイントとして、定期的な水分測定と温度確認を行います。目標水分に達したら乾燥を終了し、次の調製工程に移ります。この間、異常がないか常に監視を続け、必要に応じて条件を調整することが、高品質な乾燥麦生産の鍵となります。
乾燥後の調製作業
乾燥完了後は、品質向上のための調製作業を行います。まず比重選別により、充実度の低い軽い粒を除去します。続いて粒厚選別により、規格に満たない小さな粒を取り除きます。これらの作業により、均一で高品質な麦に仕上げることができます。
特に赤かび病の被害粒除去では、粒厚選別と比重選別を組み合わせることで効果的に除去できます。被害粒は健全粒に比べて小さく軽いため、丁寧な調製により品質向上が図れます。このような調製作業は、麦の等級向上に直結する重要な工程です。
最終工程では袋詰めを行い、適切な保管場所に移します。1袋約600kgの重量があるため、フォークリフトなどの機械を使用して安全に作業を進めます。出荷前には再度水分測定を行い、規格値を満たしていることを確認して、高品質な麦として出荷します。
乾燥機の選び方と導入ガイド
乾燥機の種類と特徴
麦用乾燥機には主に循環式と遠赤外線式があります。循環式乾燥機は最も一般的で、コストパフォーマンスに優れています。麦が機内を循環しながら熱風で乾燥される仕組みで、比較的均一な仕上がりが期待できます。構造がシンプルで保守も容易なため、多くの農家で採用されています。
遠赤外線乾燥機は、熱風だけでなく遠赤外線を併用することで、より均一で品質の高い乾燥が可能です。表面と内部の温度差が生じにくく、胴割れなどの品質低下を抑制できます。消費電力も抑えられランニングコストの削減効果もありますが、初期投資は高額になる傾向があります。
規模別の機器選択では、経営面積や処理量に応じた適切な容量選択が重要です。過大な機器は初期投資やランニングコストが高くなり、過小な機器では作業効率が悪化します。将来の規模拡大も考慮して、適切なサイズの機器を選択することが経営上重要です。
導入時の検討ポイント
乾燥機導入時の処理能力算出では、栽培面積、収量、収穫期間を考慮して必要な処理能力を計算します。一般的に、1日の処理量は総収穫量を収穫日数で割った値に余裕を見込んで設定します。また、天候不良による収穫集中も考慮し、ピーク時の処理能力を確保することが重要です。
コスト効率の評価では、初期投資額だけでなく、年間の燃料費、電気代、保守費用などのランニングコストも含めて検討します。また、乾燥により向上する品質と販売価格への影響、作業時間の短縮効果なども経済効果として評価することが必要です。
メンテナンス性も重要な検討要素です。部品の入手しやすさ、メンテナンス頻度、技術サポート体制などを確認しておくことで、長期間安心して使用できます。地域の販売店やメーカーとの関係性も、導入後のサポートに大きく影響するため、事前に確認しておくことが大切です。
トラブルシューティングと品質管理
よくある乾燥トラブル
水分ムラは乾燥作業で最も多いトラブルの一つです。原因として、収穫時の麦の水分ばらつき、乾燥機内の気流の偏り、投入量の過多などが挙げられます。対策としては、乾燥前の十分な送風、適切な投入量の管理、定期的な水分測定による監視が効果的です。
変質粒や異臭麦の発生は、収穫後の放置時間が長すぎることが主な原因です。特に高温多湿の環境下では急速に進行するため、収穫後速やかに乾燥を開始することが重要です。また、乾燥温度が高すぎる場合も変質の原因となるため、適切な温度管理を心がけます。
ビール大麦の剥皮防止では、乾燥時間と温度の両方に注意が必要です。長時間の乾燥や高温乾燥は剥皮の原因となり、麦芽としての価値が失われます。穀粒温度40℃以下を厳守し、必要最小限の乾燥時間で目標水分に到達させることが重要です。
品質劣化の防止方法
赤かび病被害粒の選別は、麦の品質管理で最も重要な作業の一つです。被害粒は人体に有害な物質を産生するため、厳格な選別が求められます。粒厚選別と比重選別を組み合わせることで、効率的に除去できます。乾燥前の仕分けも効果的で、被害粒が多い場合は別途処理することで全体への影響を防げます。
貯蔵中の水分管理も品質維持に重要です。乾燥後も梅雨などの高湿度期には水分が戻る可能性があるため、12.0%以下の低水分で仕上げることが推奨されます。また、貯蔵施設の湿度管理と定期的な水分確認により、品質劣化を防ぐことができます。
出荷前の品質確認では、水分測定だけでなく、外観検査や異臭チェックも重要です。規格外品が混入していないか最終確認を行い、適正水分を超えている場合は再乾燥を実施します。このような丁寧な品質管理により、高品質な麦として出荷することができます。
最新技術とスマート化
IoT活用による乾燥管理
最新の乾燥システムでは、IoT技術を活用した遠隔監視システムが導入されています。KSAS(クボタスマートアグリシステム)対応の乾燥調製システムでは、スマートフォンやパソコンから乾燥作業の進行状況を確認できます。温度、水分、運転時間などのデータがリアルタイムで確認でき、作業の見える化が実現されています。
遠隔監視システムにより、乾燥機の運転状況を離れた場所からでも確認できるため、夜間の管理負担が大幅に軽減されます。また、異常が発生した場合は即座にアラートが送信されるため、迅速な対応が可能になります。これにより、品質低下のリスクを最小限に抑えることができます。
データ管理による効率化では、乾燥ロットごとの詳細なデータが自動記録されます。収穫物情報、乾燥時間、燃料消費量などのデータが蓄積され、次年度の栽培や作業計画に活用できます。このようなデジタル化により、農業経営の効率化と品質向上が同時に実現されています。
省エネ・環境配慮型乾燥
燃料消費量の最適化は、コスト削減と環境負荷軽減の両面で重要です。最新の乾燥機では、熱効率の向上により従来機比20〜30%の燃料削減が可能になっています。また、排熱回収システムや断熱性能の向上により、エネルギー効率が大幅に改善されています。
環境負荷軽減の取り組みとして、バイオマス燃料の活用も進んでいます。もみ殻や木質ペレットなどの再生可能燃料を使用することで、化石燃料依存度を下げ、CO2排出量を削減できます。また、太陽光発電との組み合わせにより、さらなる環境負荷軽減が可能です。
持続可能な乾燥システムでは、機器の長寿命化と保守性向上も重要な要素です。耐久性の高い材料の使用や、予防保全システムの導入により、機器寿命の延長と安定稼働が実現されています。これにより、長期的な環境負荷軽減と経済性の両立が図られています。
コスト削減と効率化のポイント
運営コストの最適化
燃料費削減は乾燥コスト削減の最重要項目です。適切な温度管理により無駄な燃料消費を抑制し、断熱性能の向上により熱損失を最小限に抑えることで、大幅な燃料費削減が可能です。また、乾燥機の定期メンテナンスにより燃焼効率を維持し、長期的なコスト削減を実現できます。
作業時間短縮のコツとして、事前準備の徹底と作業の標準化が挙げられます。乾燥前の清掃や点検を効率化し、作業手順を標準化することで、作業時間を大幅に短縮できます。また、複数人での作業分担により、並行作業を可能にし、全体の作業効率を向上させることができます。
共同利用システムの活用は、特に小規模農家にとって有効な選択肢です。ライスセンターやカントリーエレベーターなどの共同施設を利用することで、設備投資を抑制しながら高品質な乾燥が可能になります。また、専門スタッフによる管理により、安定した品質が確保できるメリットもあります。
収益性向上の戦略
品質向上による単価アップは、最も確実な収益向上策です。適切な乾燥管理により等級向上を図り、1等米比率の向上や特別栽培米としての付加価値向上を実現できます。また、天日干しなどの特別な乾燥方法により、プレミアム価格での販売も可能になります。
出荷タイミングの最適化では、市場価格の動向を見ながら有利な時期に出荷することで収益を最大化できます。適切に乾燥・貯蔵された麦は長期保存が可能なため、価格が高い時期を狙った出荷戦略が重要です。また、契約栽培による安定価格確保も有効な戦略の一つです。
付加価値向上の取り組みとして、有機栽培や特別栽培による差別化、直販やネット販売による中間マージン削減などが挙げられます。また、6次産業化により加工品製造まで手がけることで、さらなる付加価値向上と収益拡大が可能になります。
まとめ:成功する麦乾燥のポイント
麦の乾燥は、品質と収益性を大きく左右する重要な工程です。適切な温度管理、タイミング、そして機器選択により、高品質な麦の生産が可能になります。ビール大麦では40℃以下、小麦では45℃以下の温度を厳守し、収穫後2〜4時間以内の迅速な乾燥開始が品質維持の基本となります。
品質と効率の両立では、最新のIoT技術や省エネ機器の活用により、コスト削減と品質向上を同時に実現することが可能です。また、共同利用システムの活用や、天日干しなどの特別な方法による付加価値向上も、収益性向上の有効な手段といえます。
今後は環境負荷軽減と持続可能性がさらに重要になると予想されます。バイオマス燃料の活用や太陽光発電との組み合わせなど、環境に配慮した乾燥システムの導入により、社会的責任を果たしながら収益性の向上を図ることが求められるでしょう。適切な乾燥管理により、品質の高い麦生産を継続していくことが、農業経営の安定と発展につながります。
監修者
人見 翔太 Hitomi Shota

滋賀大学教育学部環境教育課程で、環境に配慮した栽培学等を学んだ後、東京消防庁へ入庁。その後、株式会社リクルートライフスタイルで広告営業、肥料販売小売店で肥料、米穀の販売に従事。これまで1,000回以上の肥料設計の経験を活かし、滋賀県の「しがの農業経営支援アドバイザー」として各地での講師活動を行う。現在は株式会社リンクにて営農事業を統括している。生産現場に密着した、時代にあった実践的なノウハウを提供致します。
\農家さん限定!今だけ無料プレゼント/
LINE登録で「肥料パンフレット」&
「お悩み解決シート」進呈中!
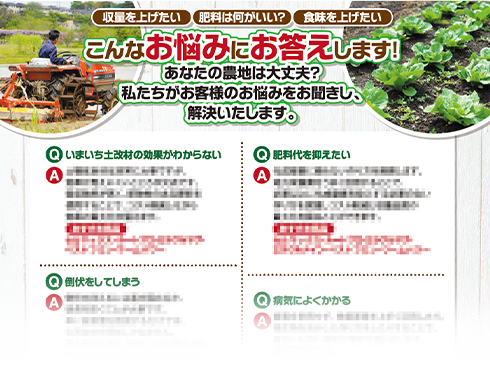
「どの肥料を使えばいいかわからない」
「生育がイマイチだけど、原因が見えない」
そんな悩みを解決する、実践的なヒントが詰まったPDFを無料プレゼント中!
プレゼント内容
- 肥料の選び方がわかるパンフレット
- 症状別で原因と対策がひと目でわかる「お悩み解決シート」
LINEに登録するだけで、今すぐスマホで受け取れます!